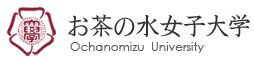乳幼児教育部門
子どもプロジェクト
乳幼児教育部門では、「子どもプロジェクト」という教育研究体制を中心に活動しています。「子ども」という存在と出会う経験を契機に、人間が生き、かかわり、成長することについて自らの問いを立てる―そのような学びを支える学部カリキュラムの創造をめざしています。'子ども'と出会う経験には、生きた'子ども'との出会いをはじめ、理論の中の'子ども'、社会的イメージとしての'子ども'、自分の中の'子ども'などいろいろな'子ども'との出会いがあります。将来どんな職業につくにしても、学生のうちに、いろいろな「子ども」との出会いを経て広い意味での保育者性(総合的保育者としての資質)が養成される必要があります。
このような問題意識のもとで、生活科学部の保育・児童学を専門とする教員が、附属幼稚園や附属いずみナーサリーの保育者、教職科目の教員とも協働しながら、授業方法・カリキュラムの改革と教育研究を進めています。
なお、この「子どもプロジェクト」は、平成18~21年度におこなわれた特別教育研究経費プロジェクト「幼・保の発達を見通した教育カリキュラム開発」=「幼保プロジェクト」を発展的に継承したものです。
「つながりの場」
◆附属幼稚園
【1】公開保育研究会
附属幼稚園では年に数回研究会が開催されています。学年別協議会の進行や全体会の話題提供をプロジェクトのメンバーが行います。
【2】園児弟妹の預かり活動支援
園内講演会や保護者会の際に、卒園児の保護者が在園児の弟妹の託児を行います。子どもプロジェクトでは大学内のプレイルームを活動場所として提供し、大学教員やプロジェクトのメンバーが子どもを観る保護者を支える立場で参加します。
【3】実習先として
教育実習生の他、「発達臨床特別実習(インターンシップ)」、「保育臨床実習」の授業において、多くの学生が実習や観察に出向きます。
◆いずみナーサリー
【1】保育研究会
ナーサリーの保育士とプロジェクトのメンバーとが月に1回程度、保育研究会を開いています。
【2】実習先として
「発達臨床特別実習(インターンシップ)」、「保育臨床実習」の授業において、多くの学生が実習や観察に出向きます。
◆愛育養護学校
東京都港区にある特別支援学校です。当プロジェクトの取り組みとして位置づけられている「発達臨床基礎論Ⅱ」の授業において、1年生および3年次編入生ら約35名が小グループに分かれ、「一日実習」に入れていただいています。また、主に3年時の選択である「インターンシップ」の受け入れ先でもあります。
◆こどもあそびばプロジェクト
板橋区蓮根地区で、養護学校や障がい児放課後クラブの元スタッフが中心になり、小学生から高校生までの障がいの子どもたちの居場所・遊びの場として不定期に開いているのがこどもあそびばプロジェクト(あそびば)です。私たち子どもプロジェクトの取り組みの一環である「発達臨床基礎論Ⅱ」の授業では、あそびばのスタッフの方の講義を受けたり、実際に活動に参加したりします。
◆自主ゼミ
【1】保育土曜ゼミ(平成19年度~)
津守眞『保育者の地平』をテキストに各自の実践を語り合う小規模ゼミです。幼稚園や保育所、特別支援学校の職員、本学および他大学の院生を中心に月に1回大学に集まり、お互いに省察(せいさつ)を深める場となっています。毎回のゼミの内容はメールで報告し、メンバーは常に共有しています。
【2】ロジャーズを保育的に読む会(平成20年度~)
保育と臨床の双方に関心をもつ、本学および他大学の院生を中心とした小規模ゼミで、C.R.ロジャーズ『自己実現の道』を読む読書会です。ディスカッションを通して、保育と臨床に通底する理論が語られていく点が興味深いです。
【3】ドゥルーズ輪読会(平成20年度~)
保育を語る言葉を探究している本学および他大学の院生を中心とした小規模ゼミです。テキストはL.クラーゲス『リズムの本質』からドゥルーズ=ガタリ『ミル・プラトー』へと移りました。「器官なき身体」の概念が、子どもの身体を読み解く上で大きな示唆を与えることを、メンバーは感受し始めています。
【4】子ども社会学研究会
「子どもを切り口に社会学しよう」をうたい文句に、子どもが登場する映画を鑑賞することを主たる活動内容とする小規模ゼミです。観た映画をもとに語りあい、それぞれの学びへとつないでいます。
成果 (平成22年度~)
◆学会発表
◇2011年度 日本保育学会 第64回大会(東京都町田市 2011.05.21-22)
<自主シンポジウム>
雑誌『幼児の教育』の現代的意義を探る
日本保育学会第64回大会発表論文集,
◇2010年度 日本保育学会 第63回大会(愛媛県松山市 2010.05.22-23)
<ポスター発表>
菊地知子(2010)
「くまのアーネストおじさん」に見る大人子ども関係の或る在り方
日本保育学会第63回大会発表論文集, 475.
塩崎美穂(2010)
イスラーム社会における子どもの保護 ―家族政策と児童福祉―
日本保育学会第63回大会発表論文集, 490.
『幼児の教育』
『幼児の教育』は明治34年(1901年)創刊の保育研究誌です。110年間、保育とかかわるたくさんの人たちと、そして少し遠くの分野の人たちと共に「子ども学」をしてきました。
自然と生活の乖離、「地域」の喪失、子育てへの忌避感、「発展」幻想の崩壊など、現代社会には子どもと大人の関係性にかかわる根本的な問題が満ち溢れている感があります。国が、現職者を含む保育者の養成に力を傾注しようとするのは当然の状況だと言えます。『幼児の教育』もまたその問題意識を共有し、「文字」と「紙」という旧来の媒体で何がまだできるのか、チャレンジを再発進しています。
本誌はこれまで月刊誌でしたが、平成23年4月にリニューアルし、3ヶ月ごと発行の季刊誌になります。読者のみなさまの自由な投稿をお待ちしています。
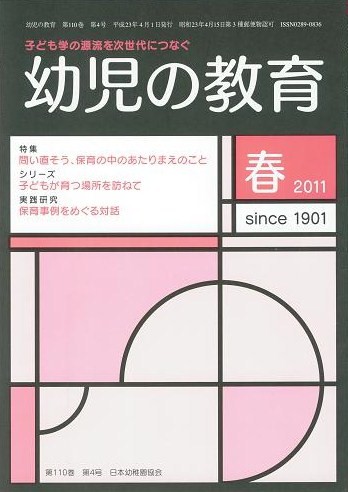 表紙について 図柄はお茶の水女子大学附属幼稚園内にあるステンドグラスの模様をデザイン化したものです |
~ 紹 介 ~ 子ども学の源流を次世代につないでいく 幼い子どもを育てること、人間が育つことの原点を見据え、「子ども」という存在を起点とする教育・保育を問い続けてきた「幼児の教育」の伝統を、新たなコーナー(視点)で引き続き繋いでいきます。社会背景や制度が目まぐるしく変化しようとも、子ども学の源流を見つめ、いろいろな理論・考え方はあっても、大切なものは変わりません。幼児教育の父とも呼ばれている倉橋惣三の理念をはじめ、様々な視点で原点から流れている大切なものを見つめ、次世代につないでいきます。 ◎特集「問い直そう、保育の中のあたりまえのこと」 ◎シリーズ「子どもが育つ場所を訪ねて」 ◎実践研究「保育事例をめぐる対話」 ◎連載「再読・倉橋惣三」ほか 全72ページ |
⇒ 活動紹介はこちら
※100年分以上にわたるバックナンバーのWEB公開も、随時更新していきます
⇒ 大学附属図書館「TeaPot」にて閲覧できます
※定期購読をご希望の方は下記メールアドレスにてご連絡ください
お問い合わせE-mail(部門共通):nyuyoji-info@cc.ocha.ac.jp
(現在、『幼児の教育』専用アドレスを取得中です。
お問い合わせの際は恐れ入りますが、件名に「幼児の教育」を明記してください。)
◇子ども学の源流を次世代につなぐ『幼児の教育』
| 巻・号 | タイトル | 執筆 |
|---|---|---|
| 第110巻第4号 (春号)p.2-3 |
プロローグ 季刊化にあたり |
浜口順子 (2011.4) |
| 第110巻第4号 (春号)p.4-12 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと1 「子どもの視点に立つ」とは? 座談会 前原 寛氏 |
<聞き手> 宮里暁美 浜口順子 |
| 第110巻第4号 (春号)p.20-23 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと1 「子どもの視点に立つ」とは? 子どもの目の高さに立つ? |
小玉亮子 (2011.4) |
| 第110巻第4号 (春号)p.24-29 |
シリーズ 子どもが育つ場所を訪ねて 大阪市立愛珠幼稚園 |
宮里暁美 (2011.4) |
| 第110巻第4号 (春号)p.30-36 |
実践研究 保育事例をめぐる対話 いなくなったカメのチュウをめぐって |
佐藤寛子 (2011.4) |
| 第110巻第4号 (春号)p.41-44 |
実践研究 保育事例をめぐる対話 カメのあとについて行く |
佐治由美子 (2011.4) |
| 第110巻第4号 (春号)p.67-70 |
論考 アーカイブズ散策(1) 百年前の入園風景 ―第11巻第4号(1911年4月)より― |
浜口順子 (2011.4) |
| 第110巻第5号 (夏号)p.2-3 |
プロローグ 大震災を受けて |
浜口順子 (2011.4) |
| 第110巻第5号 (夏号)p.4-12 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと2 子どもの「やりたい」という気持ち 座談会 安部富士男氏 |
<聞き手> 佐藤寛子 浜口順子 |
| 第110巻第5号 (夏号)p.24-29 |
シリーズ 子どもが育つ場所を訪ねて 川崎市子ども夢パーク |
宮里暁美 (2011.7) |
| 第110巻第5号 (夏号)p.30-36 |
実践研究 保育事例をめぐる対話 N子とヒマワリの種 |
上坂元絵里 (2011.7) |
| 第110巻第5号 (夏号)p.67-70 |
論考 アーカイブズ散策(2) 関東大震災直後の記事から ―第23巻第12号(1923年12月)より― |
浜口順子 (2011.7) |
| 第110巻第6号 (秋号)p.2-3 |
プロローグ 自己評価 |
浜口順子 (2011.10) |
| 第110巻第6号 (秋号)p.4-13 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと3 「子どもに寄り添う」とは? 座談会 岩崎禎子氏 |
<聞き手> 吉岡晶子 佐治由美子 |
| 第110巻第6号 (秋号)p.22-25 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと3 「子どもに寄り添う」とは 子どもと大人の具体的な生として |
金 允貞 (2011.10) |
| 第110巻第6号 (秋号)p.26-31 |
シリーズ 子どもが育つ場所を訪ねて 木の花幼稚園 |
伊集院理子 (2011.10) |
| 第110巻第6号 (秋号)p.32-38 |
実践研究 保育事例をめぐる対話 虫を探している時間 |
宮里暁美 (2011.10) |
| 第110巻第6号 (秋号)p.47-53 |
報告 『幼児の教育』誌の現代的意義を考える ―日本保育学会第64回大会 自主シンポジウムから― |
<記録> 浜口順子 |
| 第110巻第6号 (秋号)p.66-70 |
報告 子どもがいきいきと遊ぶ保育 ―フィンランド クーリッカ市の実践(1)― |
佐治由美子 (2011.10) |
| 第111巻第1号 (冬号)p.2-3 |
プロローグ 保育環境の底冷え |
浜口順子 (2012.1) |
| 第111巻第1号 (冬号)p.4-12 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと4 幼児期の「仲良し」ってどんなこと? 座談会 岩田純一氏 |
<聞き手> 伊集院理子 菊地知子 |
| 第111巻第1号 (冬号)p.13-16 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと4 幼児期の「仲良し」ってどんなこと? 小さな子の中にいて“仲良し”を考える |
中澤智子 (2012.1) |
| 第111巻第1号 (冬号)p.21-23 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと4 幼児期の「仲良し」ってどんなこと? 「仲良し」に歴史あり |
柴坂寿子 (2012.1) |
| 第111巻第1号 (冬号)p.24-29 |
シリーズ 子どもが育つ場所を訪ねて 広島大学附属幼稚園 |
高橋陽子 (2012.1) |
| 第111巻第1号 (冬号)p.30-34 |
実践研究 保育事例をめぐる対話 チョークでアート |
吉岡晶子 (2012.1) |
| 第111巻第1号 (冬号)p.35-38 |
実践研究 保育事例をめぐる対話 幼稚園でアートが生まれる時 |
刑部育子 (2012.1) |
| 第111巻第1号 (冬号)p.64-68 |
報告 保育者のまなざしの奥にあるもの ―フィンランド クーリッカ市の実践(2) |
佐治由美子 (2012.1) |
| 第111巻第2号 (春号)p.2 |
プロローグ 編集とそよ風 |
浜口順子 (2012.4) |
| 第111巻第2号 (春号)p.24-29 |
シリーズ 子どもが育つ場所を訪ねて 遺愛幼稚園 |
上坂元絵里 (2012.4) |
| 第111巻第2号 (春号)p.36-41 |
実践研究 私の保育ノートから 子どもの目線になって見えたもの |
川辺尚子 (2012.4) |
| 第111巻第2号 (春号)p.50-55 |
子ども学探訪 編輯顧問 倉橋惣三とキンダーブック 「乗物の巻」を読む |
浜口順子 (2012.4) |
| 第111巻第2号 (春号)p.56-61 |
報告 「いのちはみんなつながっている ~知識より知恵を」 本橋成一氏(映画「ナージャの村」監督)講演 |
菊地知子 (2012.4) |
| 第111巻第2号 (春号)p.62-66 |
報告 保育におけるリーダーシップ論 |
井上知香 (2012.4) |
| 第111巻第2号 (春号)p.67-70 |
アーカイブズ 幼児の教育110年の散策 阪神淡路大震災関連の記事から ―第96巻第1号(1997年1月)より― |
菊地知子 (2012.4) |
| 第111巻第3号 (夏号)p.2 |
プロローグ 子育ての季節 |
浜口順子 (2012.7) |
| 第111巻第3号 (夏号)p.4-12 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと6 「遊ぶ」ことは「学ぶ」こと? インタビュー 小川博久氏 |
<聞き手> 浜口順子 |
| 第111巻第3号 (夏号)p.24-29 |
シリーズ 子どもが育つ場所を訪ねて ふれあいの家 おばちゃんち |
佐藤寛子 (2012.7) |
| 第111巻第3号 (夏号)p.36-41 |
実践研究 私の保育ノートから 保育の学び、教科の学び |
満田琴美 (2012.7) |
| 第111巻第3号 (夏号)p.51-55 |
子ども学探訪 編輯顧問 倉橋惣三とキンダーブック 明治・対象の絵雑誌からキンダーブックへ |
浜口順子 (2012.7) |
| 第111巻第3号 (夏号)p.67-70 |
アーカイブズ 幼児の教育110年の散策 阪神淡路大震災関連の記事から(2) ―第98巻第1号(1999年1月)より― |
菊地知子 (2012.7) |
| 第111巻第4号 (秋号)p.2 |
プロローグ 待つ時間 |
浜口順子 (2012.10) |
| 第111巻第4号 (秋号)p.4-14 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと7 「共感」って何だろう? インタビュー 佐伯 胖氏 |
<聞き手> 宮里暁美 伊集院理子 浜口順子 |
| 第111巻第4号 (秋号)p.24-29 |
シリーズ 子どもが育つ場所を訪ねて バオバブ保育園ちいさな家 |
川辺尚子 (2012.10) |
| 第111巻第4号 (秋号)p.30-35 |
実践研究 私の保育ノートから 子どもとミュージカル |
榊原友里 (2012.10) |
| 第111巻第4号 (秋号)p.50-55 |
子ども学探訪 編輯顧問 倉橋惣三とキンダーブック 昭和初期の幼稚園を映すテキスト |
浜口順子 (2012.10) |
| 第112巻第1号 (冬号)p.2 |
プロローグ 親を味わう | 浜口順子 (2013.1) |
| 第112巻第1号 (冬号)p.4-12 |
特集 問い直そう、保育の中のあたりまえのこと8 「親支援」とは言うけれど インタビュー 牧野カツコ氏 |
<聞き手> 浜口順子 菊地知子 |
| 第112巻第1号 (冬号)p.24-29 |
シリーズ 子どもが育つ場所を訪ねて ゆうゆうのもり幼保園 |
宮里暁美 (2013.1) |
| 第112巻第1号 (冬号)p.36-41 |
実践研究 私の保育ノートから ごちゃごちゃと遊ぶ中で |
小川知子 (2013.1) |
| 第112巻第1号 (冬号)p.49-54 |
子ども学探訪 編輯顧問 倉橋惣三とキンダーブック ツーリズムへのいざない ~地球が小さくなり始めた時代~ |
浜口順子 (2013.1) |
◇乳幼児期の育ちと保育を考える『幼児の教育』
| 巻・号 | タイトル | 執筆 |
|---|---|---|
| 第109巻第4号 p.58-63 |
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(40) 幼保の連携に向けて ―移行期としての二歳児保育― |
塩崎美穂 (2010.4) |
| 第109巻第5号 p.9-11 |
特集 いま、倉橋と出会う5「驚く心」 「驚く心」という保育の思想 |
塩崎美穂 (2010.5) |
| 第109巻第5号 p.52-57 |
保育の現場から A夫の葛藤と変化 |
上坂元絵里 (2010.5) |
| 第109巻第5号 p.58-63 |
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(41) 学内シンポジウム「保育現場と協働して学生を育てる」を振り返って(1) |
佐治由美子 (2010.5) |
| 第109巻第6号 p.12-17 |
特集 いま、倉橋と出会う6「何にもしない」 人をないがしろにしない、保育という思想 |
菊地知子 (2010.6) |
| 第109巻第6号 p.58-63 |
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(42) 学内シンポジウム「保育現場と協働して学生を育てる」を振り返って(2) |
佐治由美子 (2010.6) |
| 第109巻第7号 p.18-23 |
特集 いま、倉橋と出会う7「うっかりしている時」 「うっかりしている時」とチャンスの訪れ |
石塚美穂子 (2010.7) |
| 第109巻第7号 p.46-51 |
保育の現場から 居場所になるということ |
伊集院理子 (2010.7) |
| 第109巻第7号 p.58-63 |
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(43) 日常性から保育カリキュラムを考える(1) 附属幼稚園『しいのみパーティー』の姿から |
宮里暁美 (2010.7) |
| 第109巻第8号 p.58-63 |
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(44) 日常性から保育カリキュラムを考える(2) いずみナーサリーにおける保育カリキュラム |
私市和子 (2010.8) |
| 第109巻第9号 p.20-25 |
特集 いま、倉橋と出会う8「いきいきしさ」 「いきいきしさ」を保育体験から考える |
佐治由美子 (2010.9) |
| 第109巻第9号 p.48-53 |
保育の現場から みんな一所懸命に生きている |
吉岡晶子 (2010.9) |
| 第109巻第9号 p.54-59 |
『幼児の教育』ネット公開に寄せて(18) 半世紀前の記事を読んで |
児玉理紗・ 金子未希 (2010.9) |
| 第109巻第9号 p.60-63 |
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(45) 「幼保プロジェクト」の成果と今後(1) |
浜口順子 (2010.9) |
| 第109巻第10号 p.9-11 |
特集 いま、倉橋と出会う9「さながら」 水の流るるがごとく、風のゆくがごとく |
佐治由美子 (2010.10) |
| 第109巻第10号 p.18-23 |
特集 いま、倉橋と出会う9「さながら」 子どもたちの育ちの力を信じて |
高坂悦子 (2010.10) |
| 第109巻第10号 p.58-63 |
お茶の水女子大学「幼・保・大」連携保育研究の試み(46) 「幼保プロジェクト」の成果と今後(2) |
浜口順子 (2010.10) |
| 第109巻第11号 p.22-25 |
特集 いま、倉橋と出会う10「子どもの心のはだ」 肌が触れて感じる温かさ |
山下紗織 (2010.11) |
| 第109巻第11号 p.26-33 |
特集 いま、倉橋と出会う10「子どもの心のはだ」 インタビュー 倉橋惣三と私(1) 森上史朗氏 |
<聞き手> 浜口順子 佐治由美子 |
| 第109巻第11号 p.58-63 |
保育の現場から イチョウの葉っぱの枕やさん |
佐藤寛子 (2010.11) |
| 第109巻第12号 p.46-51 |
インタビュー 倉橋惣三と私(2) 森上史朗氏 | <聞き手> 浜口順子 佐治由美子 |
| 第110巻第1号 p.4-7 |
巻頭言 月刊『幼児の教育』特別号のモチーフ(1) ―折り返し地点から振り返る― |
浜口順子 (2011.1) |
| 第110巻第1号 p.14-53 |
特集 創刊110年企画『幼児の教育』アーカイブズ集1 倉橋惣三の『省察』に学ぶ ―幼児教育の反省および座談会の記事から― |
佐治由美子 (2011.1) |
| 第110巻第2号 p.4-7 |
巻頭言 月刊『幼児の教育』特別号のモチーフ(2) ―「保育史」という視点を日ごろの保育に― |
浜口順子 (2011.2) |
| 第110巻第2号 p.14-53 |
特集 創刊110年企画『幼児の教育』アーカイブズ集2 保育実践者による語りや記録 ―保育を再構成する実践の知― |
塩崎美穂 (2011.2) |
| 第110巻第2号 p.58-63 |
保育の現場から 「こわれること」と「新しく始めること」 |
宮里暁美 (2011.2) |
| 第110巻第3号 p.4-7 |
巻頭言 月刊『幼児の教育』特別号のモチーフ(3) ―新しいスタートへ― |
浜口順子 (2011.3) |
| 第110巻第3号 p.14-53 |
特集 創刊110年企画『幼児の教育』アーカイブズ集3 雑誌は時代と共に、人と共に ―編み終えての語り、編集後記を中心に― |
菊地知子 (2011.3) |