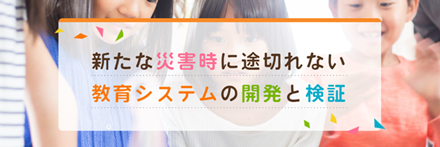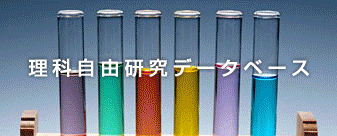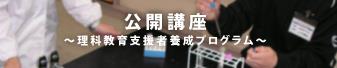- サイエンス&エデュケーション研究所
- ISEとは
ページの本文です。
ISEとは
2022年4月1日更新
サイエンス&エデュケーション研究所が目指していること
大学の使命とは、いまさら述べるまでもないことですが、"教育"と"研究"であり、最近はそれに社会貢献が付け加わっています。
教育と研究は、セットとして考えられていますが、全く異なった意味を持っています。 ためしに辞書で調べてみますと、"教育"とは「人を教えて知能をつけること」とあります。 教える内容が学問であるならば、すでに整理され秩序立てられた「美しい」世界になっているはずであり、それを学習者に吸収させるのが教育です。
一方、"研究"を辞書で調べたところ、「よく調べ考えて、真理をきわめること」とありました。 身が引き締まるような文ですね。 「美しい」世界にしっかりと立って、しかし現在は無秩序で誰も理解できない(知らない)世界に足を踏み出す行為が「研究」であり、新たな価値観や考え方を作り上げることが、研究の目的であり喜びなのです。 すなわち創造の喜びこそが研究の推進力です。
従って、研究の目的が達成されて「美しい」世界が作られたとき、研究者はそこを離れてしまいます。 残された美しい世界は、さらに体系化されて学問となり、その美しい世界を味わうとき、人は幸福になります。 でも、詰め込み教育では、なかなか味わうことができませんし、研究の喜びや楽しさは経験できません。
サイエンス&エデュケーション研究所は、不思議? 発見! 感動* を合い言葉に、科学分野における研究という作業を、大衆化させることを設立目的としています。 俳句をつくるように、新しい料理を考案するように、科学研究を行いたい、そして科学文化を作りたいと考えているのです。
- サイエンス&エデュケーション研究所 千葉和義
最近の活動
サイエンスアゴラ2021(主催:JST)において参加型ワークショップを開催
- タイトル:どんなときでも理科をあきらめない!災害時に途切れない教育セーフティネットワークとは?
- 日時:2021年11月6日(土)13-15時
- 実施形式:オンライン(Zoom)
- 参加方法:終了しました。
- プログラムや当日の動画はこちらをご覧ください。