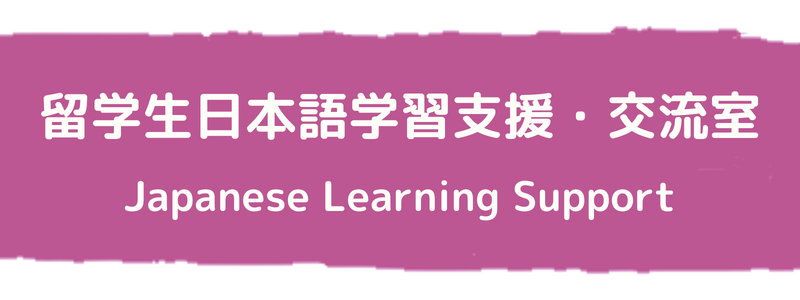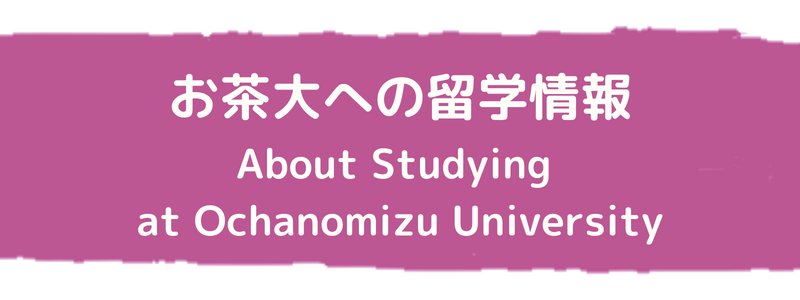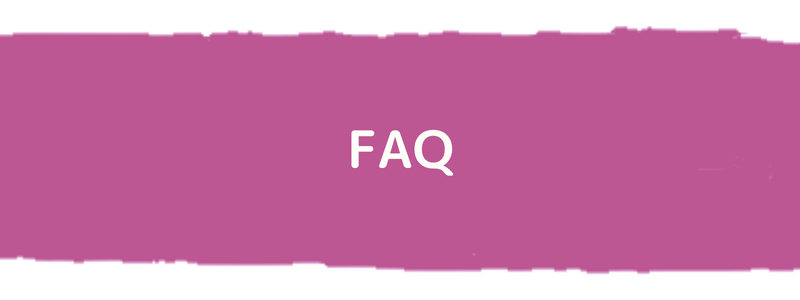- 国際教育センター【留学受入】
- 留学生教育
- レポートタイトル
ページの本文です。
レポートタイトル
2025年8月22日更新
- 2024年~2025年
- 2023年~2024年
- 2022年~2023年
- 2021年~2022年
- 2020年~2021年
- 2019年~2020年
- 2018年~2019年
- 2017年~2018年
- 2016年~2017年
- 2015年~2016年
- 2014年~2015年
- 2013年~2014年
2024年~2025年
| ドイツ | スモールレッグス・フロレンス・エレナ・イネス | 東京アイヌ ―伝統文化と現代の生活― |
| トルコ | ギョクタシュ・ハティジェ・キュブラ | 2次元マルチメディア音楽プロジェクトの流行現象を追う ―視聴者の視点からの分析― |
| インドネシア | シャロム・アガサ・プトゥリ | hololiveと推し活:日本と海外のVTuberファン文化の違い |
| 韓国 | カン・ナラ |
日本と韓国の新聞記事における外来語使用の比較研究 |
| トルコ | ババジャン・エミネ・デニズ |
外国人日本語学習者の若者言葉知識調査 |
| ポーランド | マテウシュヴ・ウツィア |
茶道と四季の変遷 ― 移りゆく季節と共に進化する茶道の美学― |
| ルーマニア | ホルバット・イオアナ |
「口」を含む日本語とルーマニア語の慣用句 |
2023年~2024年
| ベトナム | ズオン・ティ・ハ・チャン | 若者のゴミ分別意識向上の現状 ―日本とベトナムとの比較― |
| ルーマニア | シテファニカ・アナマリア・クリスティーン | ガチャにおける感情的な影響 ―なぜガチャがトレンド化しているのか― |
| ベトナム | ファム・ドアン・ゴック・ジエップ | 依頼を断る際の日本人大学生の理由選択 -ベトナム人日本語学習者の理由選択の傾向との比較- |
| 韓国 | キム・ミンギョン |
個人が少数派でいる時と多数派でいる時の行動の変化 -すれ違いの場面を中心に- |
| 韓国 | ハン・セア |
サブカルチャー音楽から読み取る若者の価値観 ―ネット発アーティストの楽曲の歌詞に着目して― |
| タイ | リンタラッタナスィリグン・アリサ |
日本の職場における外国人労働者に対しての差別問題 -タイ人の事例を踏まえて- |
| ベトナム | ノン・キー・ズエン |
宮沢賢治の作品における「本当の幸い」 -概念と影響因子- |
| ルーマニア | アトゥドレイ・ユリア・ルアナ |
松尾芭蕉の俳句とミハイ・エミネスクの詩における宇宙観の比較 |
| ブラジル | ロケ・レトリ・バーバラ | 村田沙耶香著『コンビニ人間』における性 |
2022年~2023年
| ルーマニア | バイエシュ・アストリド |
太宰治の『人間失格』とエリアーデの『近視少年の物語』における思春期の疎外感の比較 |
| ベトナム | ファーム・ザ・タイン |
『古今和歌集』の四季の歌に見られる自然観 ―ベトナム李朝の漢詩に現れた自然観との比較― |
| 韓国 | キム・ダヨン | 日本の少年漫画に見られるストーリートレンドと社会背景 |
| 韓国 | キム・ミンギョン | 日本の野球メディアの中に現れる時代別特徴 |
2021年~2022年
| ポーランド | ピヴェク・アレクサンドラ | キラキラネームの特徴と区別 |
| フィンランド | シルグレン・ユリア | 若い日本人女性の写真加工アプリ使用における特徴 |
| 韓国 | ホン・ヨンソ | 韓流によって生じる民間交流におけるジェンダーの上下関係 |
| タイ | ピスート・ブンニチャー | タイ人と日本人の納棺師に対する意識
―映画『おくりびと』を出発点として― |
| ベトナム | ファーム・ティ・トゥイ・アン | 日本で就職したベトナム人留学生の諸問題 |
2020年~2021年
| 韓国 | キム ソンウン | 「千と千尋の神隠し」の日本語版と韓国語版の比較 ―両国の文化の違いに関して― |
| ポーランド | ニジョウェック ゾフィア | 小川洋子の『密やかな結晶』におけるトラウマと思い出の描写 ―記憶とトラウマ研究の展望― |
2019年~2020年
| 韓国 | パク カリム | 潜んでいる無意識の優越感と同情―『鼻』を中心に― |
| 韓国 | チョ ソネ | 日本のスポーツ・アニメの女性キャラクターの地位―2000年代に放送されたアニメの分析を通して― |
| タイ | アサワヴェットウット ジャイサイ | 日本人とタイ人の若者における一人称の使用―女性の使用傾向を中心に― |
| イタリア | カテーナ エロイーザ | 日本の小説化 ―意義と分析― |
| ベトナム | ダオ ティ トゥエット | 日本語の形容詞の敬語表現: ベトナム人日本語学習者の使用状況 |
| ルーマニア | サフタ アナマリア カロリナ | 四季の国における季節文化 ―日本の季節文化の起源と現状― |
2018年~2019年
| ポーランド | セレジニスカ パウリナ | 現在と過去のヴィジュアル系におけるイメージの作り方 |
| ポーランド | ヴィシニェヴスカ マヤ オルガ | フェミニズムが日本とポーランドで持つ意味について |
| 韓国 | ユン へジョン | メッセンジャーにおける依頼表現の日韓比較 |
| タイ | ポープウン マンリカー | 日本語の程度(大・多)を表す副詞の使い方 |
| ベトナム | グエン チュエン ティ | ベトナム人日本語学習者から見た日本人の曖昧表現―ベトナム人学習者の観点から― |
| ベトナム | ブイ ニャット レー | 日越祖先崇拝―家族における祖先崇拝に関する両国の考え方と活動の比較 |
| 韓国 | り キョンミン | 世界は『異邦人』を作り出す―『人間失格』と『異邦人』を中心に「人間らしさ」を考察する |
| ルーマニア | サヴァ サビナ マリア | 浮世絵からアールヌーヴォーへの影響―葛飾北斎の花鳥絵シリーズ― |
2017年~2018年
|
スペイン/ イギリス |
ウンダ ベラ イレネ クララ |
日本の英語教育の問題点を探る ―高校生の会話力の観点から― |
| タイ | パウトーン ケッタカーン |
タイ人日本語学習者の動詞の省略に対する理解 ―日本人母語話者と比較して― |
| ベトナム | ホアン ティ ティエン |
ベトナム人日本語学習者のモダリティ表現の学習及び誤用状況 に関する分析―「そうだ」「みたい」「らしい」「ようだ」を中心にして― |
| ブラジル | サダ デ ケイロス ラリサ アケミ |
ブラジル日系人のコロニア語に見られる形態的特徴と バイリンガル教育について |
| 韓国 | ワン ジヨン | 韓国人日本語学習者にとっての日本語の役割語 |
| ルーマニア | プケア アンドレア ラルカ |
日本語母語話者の認識を探る ―「気」と「心」が入っている言葉とことわざに着目して― |
| 中国 | ヨウ リン |
日中女性の化粧行動に対する考え方について ―若い世代の女性観とのかかわりから― |
|
中国 (香港) |
ラム ウィン ヨン (アイリス) |
現代における若者の神社仏閣についての意識調査 ―香港と日本の比較から― |
2016年~2017年
| トルコ | エルギュゼルオール・エジェ | 日本の民間信仰における異界のもの: 妖怪 |
| イラン | ナーデルプール・ゼイナブ | 古代の日本とイランの歴史
―アケメネス朝と飛鳥時代― |
| 韓国 | ジョン・グニ | 日本の不登校の現状と対応方法 |
| ポーランド | ディハ・アガタ | ヴィジュアル系は誰のもの? |
2015年~2016年
|
韓国 |
金智賢 | 日本の広告から考える女性と社会の関わり |
|
ポーランド |
クリツカ・カロリナ | 現代の日本人と歌舞伎:
若者の歌舞伎への興味 |
|
インド |
チャンドラチュード・サムルッダ |
職場における非言語行動とマナー: インドと日本の比較 |
|
ルーマニア |
アンドレア・オニオアエア | 若者言葉:日本人でもわからない? |
|
トルコ |
バハル・ブシュラー | 日本人から見たイスラーム教 |
|
アメリカ |
ゾーイ・アリス・ウィンバーン | 現代に生きる盆栽 |
2014年~2015年
|
イギリス |
ミルバン・エラ・シャ |
日英の女性ファッション雑誌が描き出す女性像の比較 |
|
中国 |
李 小麟 |
上級日本語学習者の言語学習ストラテジー: |
|
トルコ |
クビライ・アスル |
京焼に現れる日本の美意識 |
|
ロシア |
リジエヴァ・アルタナ |
日本人と季節感 |
|
インド |
アセルカル・ヒマリ・アジャエ |
教育と放送におけるガ行鼻濁音 |
|
ポーランド |
ナタリア・ジェペツカ |
現代詩における現代日本のイメージ: |
|
スイス |
ルーギンビュール・由貴子 |
有島武郎の『星座』: |
|
イタリア |
マルタ・アンプシ |
「腐女子」について: |
|
韓国 |
朴 スルギ |
韓日関係を巡る両国20代の相互認識 |
2013年~2014年
| 中国 | 李 孝婷 |
日本人大学生の中国へのイメージ |
|
ロシア |
プシェンコ エフゲニヤ |
東京における日本大都市問題 |
|
中国 |
張 未未 |
接客場面における敬語の乱れ |
|
イギリス |
リン・ジェニー |
大学生の友人関係 ―日本とイギリスの大学生を比較して― |
|
ルーマニア |
アンドレイクッツ・マリナ |
江戸っ子の文化: 荒事「女性像」 |
| トルコ |
ギュルギュン ブルチン クトゥル |
日本人の美意識 |
|
ポーランド |
コバチェバ・アリナ |
女子大学生の政治意識: 個人と政治との関係 |
|
ポーランド |
イヴォナ・オギエラ |
『少女革命ウテナ』を通してアニメで見られる日本社会のジェンダー的問題 |
| 韓国 | 朴 惠仁 |
日本語におけるフォリナー・トークとフォリナー・ライティング |