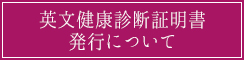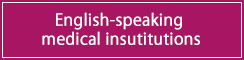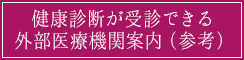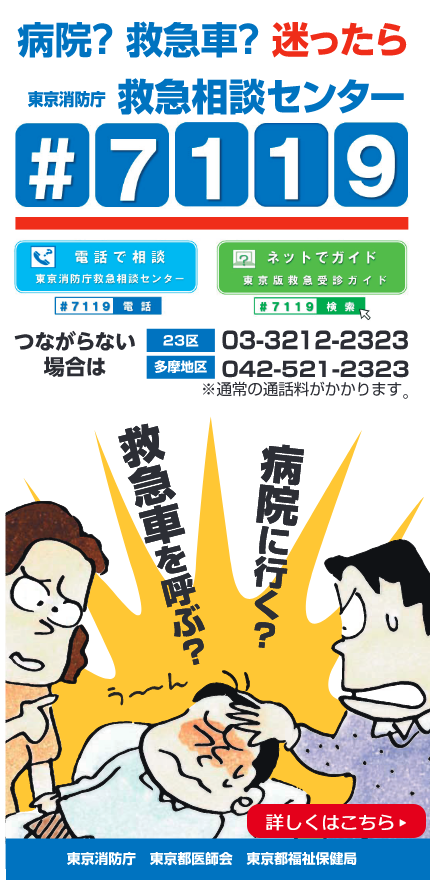ページの本文です。
感染症流行の時期を迎えています
2025年10月14日更新
各種感染症が流行する季節です
寒い季節を迎えました。今年は例年よりも早いインフルエンザの流行が確認されています。寒い季節は低温・低湿度を好むウイルスにとって最適な環境 となるため、ウィルスの水分量が減少することで空気中に浮遊しやすくなったり、体内の水分量が減少することで鼻粘膜の乾燥から感染が起こりやすい状況となります。
集団生活での感染拡大を防止するためにも、体調不良時は登校しない、早めに医療機関を受診する、ことを心がけましょう。
また、ご自身の体調不良時に備え、常備薬を準備しておきましょう(人により体質の個人差があります。薬の安易な賃借はせず、ご自身の体質に合わせたものを準備し、携行できるようにすることが良いでしょう)。
感染症について
- 感染症は、ウィルスや細菌が体内に侵入し体内で定着・増殖することで起こります。
- 感染症の原因は、「ウィルス」「細菌」がありますが、抗生物質が有効なのは「細菌」感染に対してのみです。抗生物質投与を不適切に繰り返し服用することは、耐性菌が増える主な原因となり、耐性菌の感染は、家族や周囲に広がることもあります。1980年以降、従来の抗菌薬が効かない「薬剤耐性(AMR:Antimicrobial resistance )」を持つ細菌が世界中で増えてきており、すでに、抗菌薬への耐性を持つ様々な細菌が確認されています。このため、感染症の予防や治療が困難になるケースが増えており、今後も抗菌薬の効かない感染症が増加することが予測されます。薬剤耐性(AMR)の拡大を防ぐためには、感染症にかかり抗菌薬を必要とする機会を少なくすることや感染症を周りに拡げないようにすることに加え、医療の現場で、ウイルスによる感染症を始めとして、必要のない抗菌薬を処方しないという取組が重要です。そのためには、医師に自分の症状を詳しく説明し、医師が適切な診断を下せるようにしてください。 抗生物質を処方された際には薬剤耐性(AMR)の拡大を防ぐためにも、 自身の判断で勝手に内服を中止したり、量や回数を変えたりせず、医師や薬剤師の指示を守って必要な場合に適切な量を適切な期間服用しましょう。
抗菌薬が効かない「薬剤耐性(AMR)」が拡大! 一人ひとりができることは? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp) (新しいウィンドウが開きます)
- 感染症の予防には、感染源の除去・感染経路の遮断・自身の抵抗力を高める、ことが必要です。
感染源の除去
体調不良時に登校しない、食べ物は十分な加熱をする、生ものの消費期限を守る(賞味期限とは異なります)、汚染物の密閉廃棄、換気の励行
感染経路の遮断
咳エチケット(マスクの着用)、十分な手洗い・手指消毒を行う、うがい、部屋の換気・加湿の励行、感染者の隔離
手洗いの際は、洗い残しの多い箇所に注意して石鹸を使用し、十分な手洗いをしましょう。
手を洗いましょう(手洗い手順) | 東京都感染症情報センター (tokyo.lg.jp) (新しいウィンドウが開きます)
正しく手を洗っていますか? -洗い残しはここだ!- 東京都保健医療局 (tokyo.lg.jp) (新しいウィンドウが開きます)
抵抗力を高める
予防接種を行う、栄養・休息・睡眠を十分にとり、規則正しい生活を心がける
毎日の食生活チェックブック 厚生労働省 (新しいウィンドウが開きます)
良い目覚めは良い眠りから 知っているようで知らない 睡眠のこと 厚生労働省 e健康づくりネット 解説書 (新しいウィンドウが開きます)
かぜ症候群
かぜ症候群の主な原因はウィルスによる上気道の感染です。従って抗生物質は効きません。
ご自身の常備薬として総合感冒薬を準備しておきましょう( ドラッグストアには薬剤師が常駐していますので購入時の相談もできます)。OTC(Over The Counter)薬を内服しても症状が増悪する、2~3日内服しても症状が良くならない場合は、医療機関を受診しましょう。
インフルエンザウィルス(学校感染症 第2種)
症状・治療方法について
- インフルエンザウィルスによる気道感染症で、かぜ症候群よりも重篤になりやすいことが知られています。
- 飛沫感染、接触感染によって感染し、潜伏期間は1~3日です。急な発熱、悪寒、関節痛、筋肉痛などが主な症状です。
- インフルエンザに罹患したことは、鼻腔内に挿入する綿棒を使用した抗原検査によって判定できますが、発症後12~24時間経過しないと偽陰性になることが知られています。医療機関に受診する際は、発症後の経過と時間を考慮してください。インフルエンザには発症後48時間以内に治療開始すればウィルスの増殖を抑制し、症状を1日程度短縮できる薬があります(タミフル(カプセル)、リレンザ・イナビル(吸入薬))ので、急な発熱や関節痛などインフルエンザを思わせる症状を自覚したら、適切な時期に医療機関の受診をしましょう。
- 症状が消失しても、発症から5日間(かつ解熱後2日間)は登校禁止です。周囲への集団感染を予防するためにも登校禁止期間は守りましょう。学校感染症については感染症のページ(参考1)を参照してください。
インフルエンザワクチンについて
- ウィルスの種類には「A」「B」「C」がありますが、流行するのは「A」(144種類)と「B」(2系統)で、インフルエンザワクチンがAとBを合わせた4価ワクチンが使われています(AはHA16種類×NA9種類の組み合わせでH*N*という名称が付けられます(例:H1N1など)。BはYamagata系統とVictria系統の2種類です)。
- 予防接種を受けてもインフルエンザの罹患を完全に防ぐことはできませんが、重篤化を避けるためにインフルエンザの予防接種は推奨されます。インフルエンザワクチンのワクチンを接種しなかった人の発病率(リスク)を基準とした場合、接種した人の発病率(リスク)が、「相対的に」60%減少しています。すなわち、ワクチンを接種せず発病した方のうち60%(上記の例では30人のうち18人)は、ワクチンを接種していれば発病を防ぐことができた、ということになります。インフルエンザワクチンは、そのシーズンに流行することが予測されると判断されたウイルスを用いて製造されています。日本では、インフルエンザは例年12月~4月頃に流行し、例年1月末~3月上旬に流行のピークを迎えますので、12月中旬までにワクチン接種を終えることが望ましいと考えられます。 。
- インフルエンザワクチンの接種は健康診断の受診費用と同様、病気に対する治療ではないため、健康保険が適用されません。原則的に全額自己負担となり、費用は医療機関によって異なります(3,000~5,000円程度)。
RS(respiratory syncytial virus)ウィルス
- RSウィルスによる急性呼吸器感染症で、流行期は秋がピークでしたが近年(2021年以降)は夏にピークを迎えています。潜伏期間は4-5日間で主に小児に罹患します。症状は発熱や鼻汁で多くは自然治癒しますが、時に重篤化します。大人でも罹患する場合があり、高齢者などは注意が必要です。
RSウィルス感染症Q&A 厚生労働省 (新しいウィンドウが開きます)
マイコプラズマ感染症(学校感染症 第3種)
- マイコプラズマ肺炎は、細胞に寄生する極めて小さな細菌であるマイコプラズマ・ニューモニアによる感染症です。幼児、学童期、青年期を中心に全年齢で1年を通して報告があります。
- 潜伏期間は2~3週間と比較的長いです。感染経路は飛沫感染・接触感染で、発熱、全身倦怠感、頭痛などの初発症状が現れた3~5日後に乾性の咳がみられます。咳は経過に従って徐々に増強し、解熱後も3~4週間程度続きます。
- マイコプラズマ肺炎は周期的に大流行を起こすことが知られており、日本でも1980年代では1984年、1988年に比較的大きな流行があるなど、4年周期での流行が報告されていました。1990年代以降はかつて見られた大きな流行が見られなくなった一方で、2000年以降は徐々に定点当たり患者報告数が増加傾向にあり、2011年は年間の定点当たり累計報告患者数が、2000年以降の最多報告数(2010年)を大きく上回りました。2012年は第1週から第37週まで2011年の報告水準を上回った状態が続いています。2011年から2012年にかけてこのような状態がみられている原因はよくわかっていません。
マイコプラズマ肺炎(IDWR 国立健康危機管理研究機構) (新しいウィンドウが開きます)
感染性胃腸炎(学校感染症 第3種 : ノロウィルス・ロタウィルスなど)
ノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒は、一年を通して発生していますが、特に冬季に流行し ます。 ノロウイルスは手指や食品などを介して、経口で感染し、ヒトの腸管で増殖し、嘔吐、下痢、腹 痛などを起こします。健康な方は軽症で回復しますが、子どもやお年寄りなどでは重症化したり、吐瀉物を誤って気道に詰まらせて死亡することがあります。 ノロウイルスについてはワクチンがなく、また、治療は輸液などの対症療法に限られます。 従って、皆様の周りの方々と一緒に、次の予防対策を徹底しましょう。
ノロウイルスにアルコール消毒は無効です。吐物処理には次亜塩素酸ナトリウムを希釈したものを使います。空のペットボトルに500mlの水を入れ,ハイターまたはキッチンハイターの蓋2分の1杯(または,ペットボトルの蓋2杯分)のハイターまたはキッチンハイターを入れて混ぜると,吐物処理用の消毒液ができます(吐いたらハイター)。
ノロウィルスに関するQ&A (厚生労働省) (新しいウィンドウが開きます)
消費期限と賞味期限について
消費期限(期限を過ぎたら食べない方が良い)
袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、いたみやすい食品に表示されています。
賞味期限(美味しく食べることができる期限)
袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。スナック菓子、カップめん、チーズ、かんづめ、ペットボトル飲料など、消費期限に比べ、いたみにくい食品に表示されています(作ってから3ヶ月以上もつものは「年月」で表示することもあります)。
一度開封したものは、消費期限・賞味期限に限らず早めに食べましょう。
(参考) 消費期限と賞味期限は、何が違うのでしょうか?【食品安全FAQ】 東京都保健医療局 (新しいウィンドウが開きます)
ノロウィルスについて
- ノロウィルスは、経口感染・接触感染によって感染します。潜伏期間は1~2日で、繰り返す嘔吐・下痢が主症状です。嘔吐、下痢、食物の経口摂取量の低下により脱水症状を起こしやすいので、少量ずつの水分摂取(経口補水液を中心に)をしてください。水分も嘔吐する、尿が出ない場合は脱水の進行が疑われます。早急に医療機関を受診してください。
- ノロウイルスが発生した場合、そのまん延を防ぐためには、ノロウイルスに感染した人のふん便や吐ぶつからの二次感染、ヒトからヒトへの直接感染、飛沫感染を予防する必要があります。 ノロウイルスは乾燥すると容易に空中に漂い、これが口に入って感染することがあるので、吐ぶつやふん便は乾燥しないうちに床等に残らないよう速やかに処理し、処理した後はウイルスが屋外に出て行くよう空気の流れに注意しながら十分に喚気を行うことが感染防止に重要です。
- 11月頃から2月の間に、乳幼児や高齢者の間でノロウイルスによる急性胃腸炎が流行します。 ノロウイルスは感染力が強く、環境(ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など)からもウイルスが検出されます。ノロウイルスにアルコール消毒は無効です。吐物処理には次亜塩素酸ナトリウムを希釈したものを使います。空のペットボトルに500mlの水を入れ,ハイターまたはキッチンハイターの蓋2分の1杯(または,ペットボトルの蓋2杯分)のハイターまたはキッチンハイターを入れて混ぜると,吐物処理用の消毒液ができます(吐いたらハイター®)。 (次亜塩素酸ナトリウムは金属腐食性がありますので、消毒後の薬剤の拭き取りを十分にするよう注意してください。また、亜塩素酸水もステンレス以外の金属製品に付着するとサビや変色を起こすこともありますので、薬剤の「使用上の注意」を確認してください)。
ロタウィルスについて
- 発熱、嘔吐から始まる接触感染、経口感染による感染性胃腸炎です。潜伏期間は1~2日程度で小児の罹患率が高いことが知られています。成人は症状が出ない不顕性感染であることもありますが、ウィルスは体内に持っていますので、手洗いや適切な汚染物の処理を行いましょう。
かぜや下痢の時の食事
下痢・嘔吐の時は、脱水症状に気を付けるとともに、胃腸に負担がかかるものは避けましょう。。嘔吐・下痢症状が強い場合、絶食することも一つの方法です。但し、その場合は経口補水液を中心に水分補給は必ず行ってください。
避けた方が良いもの
- 脂肪分の多いもの(肉(特に焼肉)、ラーメン、スナック菓子など)
- 糖分の多いもの(ケーキ、炭酸飲料、ココア、ドーナツなど)
- 乳製品(牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム)
- 繊維の多いもの(タケノコ、きのこ、ごぼう、レンコン、海藻類)
- 柑橘類(みかん、オレンジ、パイナップルなどクエン酸の多い果物)
- 刺身など生魚
- アルコール類
摂取して良いもの
- 経口補水液
- りんごジュース(100%)、りんごをすりおろしたもの
- お粥、うどん
- 野菜スープ
- 鶏のささみ
- 豆腐、バナナ、大根、人参、プリンなど消化の良いもの
感染を予防するために
- 食事の前やトイレの後などには、必ず手を洗いましょう。
- 下痢やおう吐等の症状がある方は、食品を直接取り扱う作業をしないようにしましょう。
- 胃腸炎患者に接する方は、患者のふん便や吐ぶつを適切に処理し、感染を広げないようにしましょう。
<食中毒予防の3原則 食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」>
食中毒は、O157やサルモネラなどの細菌に起因するものが有名ですが、食中毒の原因には、ウィルスや自然毒、寄生虫などさまざまな種類があります。
食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。
食中毒を防ぐためには、細菌の場合は、
▶ 細菌を食べ物に「付けない」
▶ 食べ物に付着した細菌を「増やさない」
▶ 食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」
という3つのことが原則となります。
食中毒を防ぐためには、細菌の場合は、
▶ 細菌を食べ物に「付けない」
▶ 食べ物に付着した細菌を「増やさない」
▶ 食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」
という3つのことが原則となります。
| 発生源 | 種類 | 症状 |
| 細菌 | 腸管出血性大腸菌(O157)、カンピロバクター、リステリア、 その他の細菌(サルモネラ、黄色ブドウ球菌、腸炎ビブリオ、ウェルシュ菌、セレウス菌、ボツリヌス菌など) |
悪寒、発熱、嘔吐、腹痛、下痢など |
| ウィルス | ノロウィルス、E型肝炎、A型肝炎 | ノロウィルス(11-2月に7割が発生) ウイルスが体に取り込まれてから半日から2日の潜伏期間を経て、嘔吐の後、水様性下痢。、2日ほどの経過で回復に向かう E型肝炎 ウイルス感染後、15~50日間(平均6週間)の無症状期間後、急な発熱、全身のだるさ、食欲不振、吐き気・嘔吐、数日後に黄疸 A型肝炎 2~6週間(平均4週間)の潜伏期間を経て、発熱や全身倦怠感、腹痛、吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振、黄疸、尿の色が濃くなる、便が白くなるなど(若年者は無症状のケースもあり) |
| 動物性 自然毒 |
フグ、二枚貝(貝毒)、巻貝(キンシバイなど)、 | フグ フグ毒(テドロトキシン)により神経と筋肉に作用し身体の麻痺 二枚貝 麻痺性貝毒:手足のしびれや頭痛など 下痢性貝毒:嘔吐や下痢の症状 |
| 植物性 自然毒 |
毒キノコ、有毒植物(水仙、ジャガイモなど) | ジャガイモ ソラニンやチャコニン(カコニン)は天然毒素の一種で、ジャガイモの芽や緑色になった部分に多く含まれ、これらを多く含むジャガイモを食べると、吐き気や下痢、おう吐、腹痛、頭痛、めまいなど クサウラベニタケ 食後20分~1時間程度で嘔吐、下痢、腹痛などの消化器系の中毒を起こす 唾液の分泌、瞳孔の収縮、発汗などの中毒症状も現れる カエンタケ(自然の多い公園にも自生しています。絶対に触らないようにしましょう) カエンタケは触れるだけでも炎症を起こし、食べると死亡事例あり |
| 化学物質 | ヒスタミン(ヒスチジンを多く含むマグロ、カジキ、カツオ、サバ、イワシ、サンマ、ブリ、アジなどの赤身魚及びその加工品) | 食べた直後から1時間以内に、 顔面、特に口の周りや耳たぶが紅潮し、頭痛、じんましん、発熱など |
| 寄生虫 | クドア(生食用生鮮ヒラメ(ヒラメのお刺身等) )、 アニサキス(アニサキス幼虫は、サバ、アジ、サンマ、カツオ、イワシ、サケ、イカなどの魚介類に寄生 |
クドア 食後数時間程度で一過性の嘔吐や下痢を呈し、軽症で終わる症状が特徴 急性胃アニサキス症食後数時間後から十数時間後に、みぞおちの激しい痛み、悪心、嘔吐 急性腸アニサキス症 食後十数時間後から数日後に、激しい下腹部痛、腹膜炎症状 |
引用:厚生労働省_健康・医療_食中毒 (新しいウィンドウが開きます)