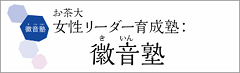- グローバルリーダーシップ研究所
- イベント
- IGLセミナー「ジェンダー平等社会の実現を目指して:縮まらないジェンダー格差:要因と未来への道筋 ジェンダー法学の視座から」開催報告
ページの本文です。
IGLセミナー「ジェンダー平等社会の実現を目指して:縮まらないジェンダー格差:要因と未来への道筋 ジェンダー法学の視座から」開催報告
2025年1月24日更新
三成美保氏(追手門学院大学教授)に「ジェンダー平等社会の実現を目指して」と題してご講演をいただきました。
三成氏によれば、ジェンダー平等とは、法的平等(平等を実現するための手段)と、実質的平等(格差解消の根拠としての統計数値)の2つがあり、現状、日本はいずれも不備の状態です。選挙でクオータ制を導入している国々が軒並み格差解消に向けて進展しているのに対し、導入していない日本は格差解消の後進国となっており、世界の中の日本の現状が、具体的で詳細な数値と図によって明示されました。
三成氏は、日本はかつて、戦後の民主化の中で法的平等の先進国であったと述べました。憲法第24条は近代的家父長制を否定し、個人の創出と公私にわたる男女平等を目指しました。しかし21世紀を迎えた今、日本のジェンダー平等は頓挫し、停滞期に入ってしまいました。その要因として、ジェンダーバックラッシュやアンコンシャスバイアスが女性の地位上昇を抑制したほか、経済停滞や少子化が重なって家族主義や宗教右派の強まりがあげられるとし、そうしたことが日本のジェンダー平等実現を阻んだと述べました。ヨーロッパなど世界各国がクオータ制を導入してジェンダー主流化に向けて舵を切る中、実効性の乏しい法改正で日本の法的平等は停滞してしまったといいます。2006年、教育基本改定に家族主義が盛り込まれ、ジェンダー平等が後退しました。民主党政権下でその家族主義が再否定されたものの、2012年に自民党が復権すると、再び家族主義が議論され始めました。憲法第24条に家族主義の復活が盛り込まれた憲法改定案(2012)が議論され、日本のジェンダー平等はふたたび停滞の一途をたどることとなりました。
三成氏は未来に向けて、3つのバイアス壁(社会・家族・自分の心の壁)を取り除く必要があると主張しました。そのためには、関連法案の改正や人権の法整備、さらにはクオータ制の導入など政治の場における男女均等法の強化を含む法的整備が不可欠であると述べました。人間は本質的に「ケアされる弱い存在」であるという前提に立ち、ケアを女性に任せる「自助」ではなく、「公助」というシステムの確立を訴えました。
明るいニュースとしては、最近、最高裁はジェンダー平等の原則に基づいて様々な法令の違憲判断を出していることです。三成氏は、法制度の改革によって、人々が「あたりまえの呪縛」から解放され、意識が変化し、その「意識」が社会変革を生み出す可能性を述べ、ジェンダー平等実現に向けての道筋を示しました。
講演後、参加者からは「興味深く、わかりやすくひきこまれた」「包括的な客観的な指標で現状をよく理解できた」「自分の中にある家族主義に気づきがあった」「多角的な取り組みが必要とわかった」など新たな視点や学びがあったことに多くの感動の声が寄せられました。
文責:麻生奈央子(グローバルリーダーシップ研究所 特任講師)