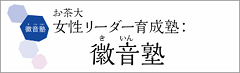- グローバルリーダーシップ研究所
- イベント
- IGLセミナー「ジェンダー格差はなぜ維持されるのか:社会心理学の視点から格差維持の心の仕組みを考えてみる」開催報告
ページの本文です。
IGLセミナー「ジェンダー格差はなぜ維持されるのか:社会心理学の視点から格差維持の心の仕組みを考えてみる」開催報告
2025年2月4日更新
森永康子氏(広島文教大学教授)に「ジェンダー格差はなぜ維持されるのか」と題してご講演をいただきました。
森永氏は「私たちは(喜んで)格差を受け入れてしまう傾向がある」と本日の結論を最初に説き、その後、格差維持の心の仕組みについて、社会心理学の研究を解説しました。まず、ジェンダー格差是正の取り組みにおいて、「30%」という数値目標についての研究が紹介されました。組織で働く人の中で女性の占める割合の目標を「50%」とするのは女性に有利すぎ、男性に不利すぎると人々は認識しやすく、「30%」が適切な数値目標と考える傾向があることが紹介されました。「なぜ50%ではなく30%で満足してしまうのか?」という森永氏の問いかけに、参加者はその後に続く森永氏の丁寧な解説に惹きこまれていった様子でした。
社会心理学の理論で「システム正当化理論」があります。人々は現状維持に動機づけられており、現状を肯定することで心理的安寧を得るという理論です。森永氏は、同理論に基づいて様々な社会心理学研究を展開しており、その実証研究が紹介されました。
日本は世界的にもジェンダー格差が大きい。しかし、日本の女性の主観的幸福感は男性と比べて同程度または男性よりも高いことが報告されている。森永氏は、ジェンダー格差社会において日本の女性は現状の性役割を肯定することで幸せを感じている可能性を検討しました。分析の結果、現在のジェンダー格差社会のシステムを肯定化し正当化している女性ほど、人生満足感が高いことが示されました。つまり、日本の女性は格差社会における性役割を受け入れ、肯定化することで幸福感を感じていることが示されたということです。森永氏は、その他のご自身の研究についても具体的な数値を示しながら丁寧に解説してくださいました。
森永氏は、ジェンダーシステム正当化の関連で「好意的性差別」についての研究も行っています。同差別は、表面的にはポジティブで一見温情的ではあるゆえに差別とは認識されにくいものの、「女性は弱い」「女性は仕事ができない(無能だ)」とのステレオタイプが根底にあることが特徴です。森永氏は、数学の成績で高得点をとった女子高校生に「女の子なのにすごいね」と褒めた群と、「すごいね」と褒めた群を比較しました。その結果、前者の女子生徒の意欲が低下したという心理学実験の結果を紹介しました。好意的性差別は女性の自信や意欲を失わせ、あからさまで敵対的な性差別よりも時に悪影響をもたらす可能性があるといいます。こうした実証研究について森永氏は図やイラストで分かりやすく説明をしてくださいました。講演後、「一言増えるだけでこんなに違うんだと驚いた」との感想が寄せられるなど、好意的性差別の森永氏の研究に多くの関心が寄せられました。
約100名を超える多数の方々が学内外から参加しました。講演終了後には数多くの質問がなされ、「学びが深まった」「ハッとさせられた」「衝撃を受けた」と感想が寄せられました。参加者は森永氏の丁寧で詳しい解説に聞き入り、多くの学びを得て、参加者は実りある午後の時間を共有したと思われます。
文責:麻生奈央子(グローバルリーダーシップ研究所 特任講師)