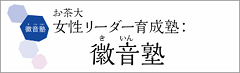- グローバルリーダーシップ研究所
- 研究所紹介
- 特別研究員制度
ページの本文です。
特別研究員制度
2025年10月14日更新
みがかずば研究員
女性研究者のための研究継続奨励型「特別研究員制度」
(呼称「みがかずば研究員制度」)の創設
本学では2012(平成24)年度より、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ女性研究者の養成・確保に資するため本学独自の特別研究員(呼称:みがかずば研究員)制度を導入しました。
すぐれた女性研究者の継続的な研究活動を支援するともに、女性研究者が研究中断後に円滑に研究現場に復帰する機会を提供します。
公募・求人情報はこちら(新しいウインドウが開きます)
みがかずば研究員 採択後の進路
| みがかずば研究員採択年度 | 2024年度 (令和6) |
2023年度 (令和5) |
2022年度 (令和4) |
2021年度 (令和3) |
2020年度 (令和2) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用人数 | 11 | 7 | 12 | 7 | 13 | ||
| みがかずば研究員(継続) | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||
| 任期の 定めの ない ポスト |
国公立 大学 |
教授 | |||||
| 准教授 | 1 | ||||||
| 講師 | |||||||
| 助教 | |||||||
| その他 | |||||||
| 私立 大学 |
教授 | 1 | |||||
| 准教授 | 1 | ||||||
| 講師 | 1 | ||||||
| 助教 | |||||||
| その他 | |||||||
| その他 | |||||||
| 任期の 定めの ある ポスト |
国立大学 | 1 | 1(講師) | 1(講師) | 1(講師) 1(助教) |
||
| 私立大学 | 1(助教) | 1(講師) | 1(准教授) 1(講師) |
||||
| 研究員 | 2 | 1 | |||||
| その他 | 1(RF) | 1(RF) | 1(RF) | ||||
| その他 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
RF:リサーチフェロー
AF:アソシエイトフェロー
2025(令和7)年度 みがかずば研究員
中村 美和子
| 専門分野 | 教育文化史、児童文化史 |
| 研究内容 |
キーワード:ラジオ、子ども、童話、国家主義、教育 日本におけるラジオ初期(1925–1945)の子ども番組の歴史を調べています。対象とするのは、放送童話を中心とするコンテンツと番組普及目的の広報のありようです。ラジオは戦争遂行に貢献しましたが、日本が戦争に向かう時代に、子ども番組と広報にどういう変化が生じたのかを実証的に検討しています。大人が子どもに働きかけることの意味について、深い関心を寄せています。 |
岩田 優子
| 専門分野 | 環境創成学、地域開発学 |
| 研究内容 |
キーワード:環境社会システム、サステイナビリティ、協働ガバナンス 急速な少子高齢化に直面する日本の地方都市を対象に、地域の人材や資源を生かした地域社会イノベーションの創造プロセスについて研究してきました。博士論文では、特に、「協働ガバナンス」の分析枠組みを用いて、地域社会イノベーションの創出要件の一端を明らかにしました。本年度は、昨年度の調査研究結果を受け、協働の場における「多様な知の統合」の観点から、研究をより一層深めたいと考えています。 |
坂爪 明日香
| 専門分野 | 動物生理学、生物物理学、重力生物学 |
| 研究内容 |
キーワード: サンゴ、幼生、水棲微小生物、重力走性、着生、分散 海底で固着生活を送る大人のサンゴにも、受精後から数週間ほどの間、海中を浮遊する幼生の時期があります。幼生は全身に生える多数の繊毛を使い、自身の持つ遊泳能力と海流によって移動します。海底の適した場所に辿り着くと着生し、ポリプへと変態後、分裂によって大人のサンゴの姿に成長します。浮遊生活の中で、幼生がどのように上下方向を認識し、水面と水底の間を直進することができるのか、そのしくみに興味を持って研究しています。 |
宇野 和
| 専門分野 | 日本語学 |
| 研究内容 |
キーワード:ネット集団語、若者ことば、Twitter 私は現代日本語における集団語や若者ことばに興味を持っています。これまではTwitter(現X)で多く用いられる「つらみ」「ねむみ」のような新語形(新しいミ形)を研究してきました。逸脱表現だと言われることの多い集団語や若者ことばですが、それらを切り捨てるのではなく、なぜ用いられるようになったのか、どのような機能を持っているのかを研究することで現代語の日本語表現の傾向を探りたいと考えています。 |
崔 暁文
| 専門分野 | 第二言語習得、日本語教育、認知言語学 |
| 研究内容 |
キーワード:多義動詞、未知拡張義、意味推測 多義動詞の未知拡張義の意味推測の正確さは、学習者のL2習熟度、中心義との意味的関連性及び文脈情報量の影響を受けることが明らかにされている。しかし、中国語を母語とする日本語学習者の推測プロセスを詳細に分析したところ、「母語訳との漢字の対応関係」も推測の正確さに影響を与えることが観察された。そこで、①中心義との意味的関連性と②母語訳との漢字の対応関係の2側面から推測の正確さに与える影響を再調査する必要がある。 |
清水 理佳
| 専門分野 | 位相幾何学 |
| 研究内容 |
キーワード:結び目、結び目理論、組みひも 結び目理論では、ひもを絡ませて両端を閉じたもののことを結び目とよびます。また、複数のひもを束ねて編んだもののことを組みひもといいます。私は結び目や組みひもの幾何的な性質について、図式的・組み合わせ的に研究しています。最近は、組みひもの図式から得られるある行列から、結び目や組みひもの絡まり具合を表す量を取り出すことに興味をもって取り組んでいます。 |
山本 夏生
| 専門分野 | スポーツ社会学、ジェンダー、メディア研究 |
| 研究内容 |
キーワード: スポーツ、ジェンダー、スポーツ政策、子育て世代 女性のスポーツ実施率の数値の低さが問われる中で、その実態に、より解像度を上げて迫りたいと考えています。令和6年度「スポーツの実施状況等に関する世論調査」でも、例年の通り特に30~40代の女性、いわゆる働き世代・子育て世代の女性のスポーツ実施率が低いという結果が出ています。アンケート調査、フィールドワーク調査、さらにはSNSの発信を追いかけてその世代の現状をコロナ禍にも絡めて解き明かしたいと考えています。 |
髙島 優季
| 専門分野 | 栄養生化学、食品科学 |
| 研究内容 |
キーワード: 多価不飽和脂肪酸、代謝性脂肪肝炎、腸肝軸、胆汁酸 脂肪肝の原因は肥満や過剰なエネルギー摂取だと考えられがちですが、日本やアジア諸国では患者の約3割は非肥満者です。近年、食事性脂質の「質」の低下と肥満を伴わない脂肪肝の関連が指摘されていますが、その分子機構は未解明です。現在は特に、肝臓と腸管の相互作用に着目し、なぜ脂質栄養の低下により脂肪肝を発症するのかを研究しています。 |