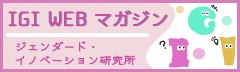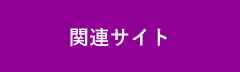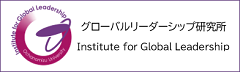- ジェンダード・イノベーション研究所
- イベント等情報
- 【開催報告】2024年度第1回IGIセミナー
ページの本文です。
【開催報告】2024年度第1回IGIセミナー
2025年3月11日更新
建築学からみたジェンダード視点でのイノベーションへのアプローチ
開催概要
【日時】2024年6月19日(水曜日)10時~11時
【講師】長澤夏子教授(基幹研究院自然科学系(建築学)/IGI研究員)
【開催方法】オンライン
【参加者数】52名
開催レポート
2024年6月19日(水)、2024年4月に新設された共創工学部の長澤夏子教授を講師にお招きして、IGI学内セミナー「建築学からみたジェンダード視点でのイノベーションへのアプローチ」をオンライン形式で開催した。参加者は33名の学生を含む52名と盛況であった。
長澤教授は、都市・建築を対象としたジェンダード・イノベーションのプロジェクトに取り組んでいる。本セミナーでは、三井不動産とお茶の水女子大学の共同研究「働く場と生活の場における女性の起業支援に関する研究および社会実践」の成果の紹介と、建築視点のジェンダード・イノベーションとして目指すべきゴールやそこに至るための方法論についての見解をお話いただいた。
都市・建築は公共性が高いものであることから、「男女共に利用できる」ことが望ましいという建築思想がある。そのため、建築の利用では「男女差がない」ことを確認することが重視されてきた。ジェンダード・イノベーションは「性差」を取り入れるという点で、これまでの建築思想とはやや異なるアプローチとなる。
近年、工学分野では、女性の技術者・研究者が少ない背景があり、開発のなかに女性視点が不足しているという懸念が示されている。あわせて、都市・建築への適用に、社会的あるいは生物学的な男女差に配慮することで、より公共性の高い開発への期待が高まっている。つまり、都市・建設分野でも、男女差を見ることで、新たな発見やイノベーションを生み出すことが目指すべき最終ゴールとされ始めている。
三井不動産株式会社との共同研究では、起業に関するジェンダー差を見ることで、都市不動産の新しい価値の提案、社会実装を目指している。研究を進めるうえで、起業とジェンダーについて造詣が深い、鹿住倫世教授(専修大学商学部 教授/IGI客員教授)にご指導をいただいた。
日本の女性起業家は、2022年の調査で男性の4分の1程度であり、他国と比べても低く、業種はライフイベントにかかわる医療・福祉や飲食・サービスに偏っている傾向がある。起業家への投資を行うベンチャーキャピタルの代表を見ると99%が男性であり、起業支援、創業支援は女性向きではない可能性があることが指摘されている。
そこで、女性の起業支援に力を入れている創業支援施設(10カ所)を調査した。女性は男性よりもライフイベントをきっかけとして起業する傾向にあることから、ソフト面の支援として、フェーズ0の状態から1歩を踏み出すための支援やライフスタイルビジネスの起業支援、同性の仲間が集う場所などが提供されていることが分かった。ハード面では、住宅街に近い場所でのテストマーケットショップや起業内容の地域差に配慮したイベントの実施、創業支援でまちづくりの一部を担う機会の創出、託児室や出入り自由の図書スペースの設置など、特色のある設備・サービスがあり、女性が気軽に立ち寄るための工夫がされていた。
次に、女性の起業家がどのような場所で働いている/働きたいかを明らかにするための調査を行った。起業者(男性515名・女性515名)と起業意向者(男性515名・女性515名)に対してWEBアンケート調査をしたところ、女性の起業者は30~40代が多いのに対して、男性の起業者は40~60代と起業年齢が遅い傾向があった。立地特性では、女性は「住宅」が多く、男性は「オフィス街」「農業地域」「工業地」が多かった。これには業種・職種の影響と、家事などとの両立の度合いがあり、その結果、理想の仕事場として女性が「自宅」や「常設店舗」を好み、男性は「常設オフィス」を好む傾向があった。また、創業支援施設の利用ニーズをみると、女性は「カフェ」や「託児室」のニーズが高く、男性は「喫煙室」「シャワー室」のニーズが高いといった違いがあった。女性起業家の支援に、現在の都市計画の基本である「職住分離を基本とした用途地域」を再考し、ワーク(職場)とライフ(居住地)がシームレスになる環境整備や身近な場所での起業支援を充実することは、これまで見落とされていた視点である。
そこで、性別のほかに、都市部と地方、子どもの有無の要因を加えて分析をした。その結果、都市部の起業家は男女とも住宅街を選び男女差はないが、地方の男性起業家は住宅街を選ばないことが分かった。これは、都市部と地方の業種、業務形態の違いが関係していると思われる。都市部では共働き向け住宅に働きやすい設計の工夫をすることで、女性の起業家の支援につながる可能性がある。
子どもの有無による違いをみると、子どもがいる男性は女性と同程度にライフを優先していることが分かった。これにより、女性のニーズが高い働く場・サービスは、子どもがいる男性起業家にも利用される可能性があることが分かった。
ジェンダード・イノベーション視点の研究では、女性のための提案をするといった狭い視点ではなく、女性目線のサービスを実現することで、それ以外の人にどのような影響があるかを検討することが大切だ。加えて、「社会調査結果に基づかない実践」も必要かもしれない。なぜなら、現在の環境をもとにした調査では、サービスが提供されていない場合に、ニーズの有無そのものが認識できない限界がある。ニーズがなくても、提供してみることによって、新しい認識が発見されることもある。だからこそ、調査・分析で導き出したニーズだけでは不十分で、「ない」ことも発見したうえで、新しい提案、展開につなげたい。
約50分の講演後に質疑応答の時間が設けられた。「(地域差や子どもの有無、ニーズ調査などの)研究の結果を踏まえた今後の展開を教えて欲しい」といった質問があった。長澤教授からは、「たとえば、女性の起業者にコワーキングスペースのニーズが「ない」という結果が出たが、その結果からコワーキングスペースの検討を省くのではなく、むしろ男性向けのコワーキングスペースを見直して女性視点のしつらえ方を加えるなど、具体的な空間提案を念頭に置きながら実装化したい」との回答があった。
本セミナーで紹介されたプロジェクトの詳細は、note「&ジェンダード・イノベーション 三井不動産×お茶の水女子大学」で参照することができる。
記録担当:高丸理香(IGI 特任准教授)