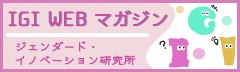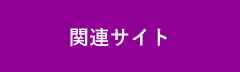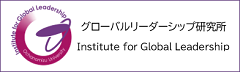- ジェンダード・イノベーション研究所
- イベント等情報
- 【開催報告】2024年度第2回IGIセミナー
ページの本文です。
【開催報告】2024年度第2回IGIセミナー
2024年12月16日更新
GISベースの通勤・送迎行動シミュレーションから可視化する大都市における職住育の関係
開催概要
【日時】2024年10月30日(水曜日)10時~11時
【講師】宮澤仁教授(共創工学部文化情報工学科 学科長(地理学))
【開催方法】オンライン
【参加者数】21名
開催レポート
2024年10月30日(水)、IGI学内セミナー「GISベースの通勤・送迎行動シミュレーションから可視化する大都市における職住育の関係」がオンライン形式で開催された。地理情報学、福祉地理学、都市地理学が専門の宮澤仁先生に講師をお願いし、大都市部で課題となっている仕事と家庭生活の両立、そして保育所の整備について、GIS(地理情報システム)を用いた分析結果を説明いただいた。
まず、宮澤教授が分析に用いているGISの紹介があった。GISは、地球上の様々な事象の位置情報を管理・加工、可視化、分析できる技術である。日常生活では、インターネットの地図サービスやカーナビゲーションシステムに利用されている。また学術分野では、地理学にとどまらず、考古学や疫学・公衆衛生学、都市計画でも活用されており、学際的研究の共通基盤となっているという。
つぎに、時間地理学の基本概念と交通計画学おける概念の応用について説明があった。特に印象的であったのは、日常生活の行動や状況が女性と男性では異なるため、交通行動にもジェンダーによる違いがみられることである。たとえば、女性は男性に比べて、仕事以外の用事が多く、家事やケアにともなって移動が発生することから、移動距離が短い、移動頻度が多いという特徴がある。またパートタイム雇用が多く、勤務スケジュールが多様である、自宅近くで就労する傾向がみられることから、ピーク時間以外の移動が多い、立ち寄る箇所や目的地が多いことも確認されている。さらに賃金が低く、運転免許の保有率が低いために、比較的安い移動手段を利用する、自家用車の利用率が低いことも分かっている。このような交通行動におけるジェンダー差は、指摘されるまで気がつかないことも多いのではないだろうか。
本セミナーの主題について、宮澤教授によるシミュレーションでは、東京駅周辺を職場とした場合、保育所の開所・閉所時間という制約の中で、保育所送迎と就業の両立が可能なのは、東京都心から15〜20km、23区の範囲であるという。家から保育所までの送迎手段によっても有効地域に差がみられ、徒歩で送迎する場合には、保育所利用の有効地域は小さいが、自転車で送迎する場合には、かなり拡大する。また23区外では、駅に近く、保育時間が長い施設に利用が限定されることも示された。以上から、保育所の開所・閉所という時間制約をうける育児期の保護者(職場が都心の場合)は、23区内や駅近くに居住し、職住近接を実現することが有効であるといえる。
しかし昨今は、23区内の住宅価格が高騰しており、ファミリー世帯が住宅を取得するには、郊外を選ばざるを得ない状況になっている。そこで宮澤教授から、郊外地域で送迎保育を導入している自治体の紹介があった。駅周辺に小規模な送迎保育ステーションを設置し、保護者は朝と夕、子どもをステーションまで送迎する。認可保育所の保育時間外については、子どもは保育ステーションで過ごす。一方保育時間内については、子どもは認可保育所までバスに乗って移動し、保育所で過ごすこととなる。これによって、送迎に便利で待機児童が発生しがちな駅に近い保育所と送迎がしづらく空きが発生している駅から遠い保育所の需給バランスが解消し、都心へ通勤するために長時間保育を希望する保護者のニーズにも対応できるという。
セミナー後の参加者アンケートでは、送迎保育ステーションは未就学児にとって体力面、精神面での負荷が多いのではないかという質問があった。宮澤教授からは、バス移動による1日の中での環境の変化、保育時間の長時間化、保育施設の職員と保護者の関係が希薄になりがち等の課題があると回答があった。また幼稚園を送迎先とする送迎保育も増えてきているとの補足があった。詳細については、先生の論文(宮澤仁・若林芳樹 2019, 関真由子・宮澤仁 2024)を参照されたい。
本セミナーでは、女性と男性では生活行動が異なり、それにともなって交通行動にも違いがみられること、GISを用いて地図上で可視化することで、就業と保育所送迎を両立することができる地域を視覚的にわかりやすく学ぶことができた。
記録担当:相川頌子(IGI 特任講師)