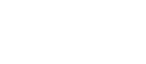- ジェンダード・イノベーション研究所
- 活動報告
- 【開催報告】2023年度第4回IGIセミナー
ページの本文です。
【開催報告】2023年度第4回IGIセミナー
2024年2月29日更新
細胞の性差
開催概要
| 日時 | 2024年1月24日(水曜日)10時~11時 |
|---|---|
| 講師 | 相川京子(基幹研究院 自然科学系 教授) |
| 開催方法 |
オンライン |
| 参加者数 | 34名 |
開催レポート
2024年1月24日(水)、IGI学内セミナー「細胞の性差」がオンライン形式で開催された。糖鎖生物学、細胞生化学が専門の相川京子先生に講師を依頼し、細胞における性差についての最新の研究動向を紹介していただいた。身体に性差があることは周知のとおりだが、身体を構成する細胞にも性差があるということは多くの人はまだ認識していないのではないだろうか。本セミナーでは、そもそもヒトは何個の細胞でできているのだろうかという基礎的な知識から、生命科学研究において性差が意識されるようになった機運、これまでは性的二型性がないと考えられてきた臓器由来細胞におけるエストロゲンの作用について糖鎖科学の観点から説明していただいた。
一般的に、ヒトの細胞の数は、体重60kgと想定し、細胞1個1ngとして60兆個と見積もられている。しかし、ヒトの細胞の大きさは様々であるため、単純に60兆個としてよいのだろうか。全身の組織と器官ごとに細胞数を計算したBianconi et al.(2013)によると、体重70kg、身長172cm、体表面積1.85m2、30歳の平均的な男性の細胞数は37兆2,000億個あるという。では、女性の細胞どのくらいあるのだろうか。性や身体的な特徴などの多様性に配慮した研究が今後も必要になるだろう。
研究用の細胞を提供する理化学研究所バイオリソース研究センターに保管されているヒト、マウス、ラットの細胞の性別には偏りがあり、全て男性由来の細胞の方が多い。その理由としては、動物実験では、オスの方が使用しやすいからだという。ある特定の性のみを扱った実験結果が、あらゆる性に適応されていることで生命にかかわる重大な見落としが生じるという事実を知っておく必要がある。
生命科学研究において性差が意識されるようになった歴史的な流れについて、1985年に米国国立衛生研究所で女性特有の病態の研究が始まり、1995年米国食品医薬局にOWH(Office For Women’s Health)が創立された。日本では、1990年代に性差医学に関する勉強会が始まり、2002年に性差医学・医療学会が立ち上がった。性差医学とは、発症率に男女差がある、あるいは発症率が同程度でも臨床的な経過において男女で違いが見られる病態を対象とした学問分野である。
性差医学が発展する以前から、生物学の研究領域では、性別は単純に二分化できるものではないという理解が進んでいた。ヒト以外の様々な生物の観察や研究と通して、擬態などによってオスメスの判断ができない生物種がいることから、オスとメスが対極にあるのではなく、性は連続して変化していく(スペクトラム)と捉えられている。ヒトの一生においても性はスペクトラムにあると言えるのではないだろうか。どの発達段階かによって性スペクトラムのどの位置にいるかは異なると言われている。
相川先生は以前から血栓症にかかわるタンパク質や糖鎖の研究をしていたという背景から、ジェンダード・イノベーションの観点を踏まえ、女性ホルモンに血栓形成抑制作用があるのはなぜか、女性ホルモンによって肝臓や唾液腺から産生される血液凝固タンパク質の量や質(糖鎖)が変化するのか、という研究テーマに取り組んでいる。女性ホルモンとして知られているエストロゲンは、体内でコレステロールから作られる。生殖腺が主な産出部位とされているが、生殖腺以外でも少量ではあるが産生される。エストロゲンには作用が異なる3つの受容体(ERα、ERβ、GPER)があり、それぞれ作用が異なる。それぞれが、性的二型性(性別によって個体の形質が異なること)がみられる器官(生殖器、脳、乳腺、筋)以外にも、肝臓や肺など、様々な臓器で発現していることが明らかになっており、幅広い組織がエストロゲンの作用を受けている可能性があることが明らかになっている。
今回のセミナーでは、生物学的領域における性差のとらえ方、オス、メスの二元論ではなく性スペクトラムとして性をとらえる有効性、一見性差は関係がなさそうな肝臓や唾液線といった器官にも女性ホルモンの受容体が存在するということを学ぶことができた。
 セミナーの様子:相川京子教授
セミナーの様子:相川京子教授
記録担当:山本咲子(IGI 特任リサーチフェロー)