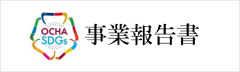- SDGs推進研究所
- 令和7年度第2回SDGs研究助成 成果報告会のご案内
ページの本文です。
令和7年度第2回SDGs研究助成 成果報告会のご案内
2025年5月21日更新
本イベントは終了しました。開催報告の記事をご覧ください。(こちら)
※本案内は、学内関係者向けです。
令和7年度第2回SDGs研究助成 成果報告会のご案内
SDGs推進研究所は、個人研究、学内外の研究者との共同研究、企業や他機関との共同研究などを対象とし、本学のSDGs研究を牽引する研究を発掘し、SDGsに資する研究活動および教育活動を活性化させることを目的とした助成を行っています。
この度、令和6年度に実施した研究助成の成果報告会を3回にわけて開催する運びとなりました。学生、教職員皆様のご参加をお待ちしております。お近くの学内者へ、ぜひご周知ください。
第2回は、嶌田智先生 (理学部)、水村真由美先生(文教育学部)、古川はづき先生(理学部)、河野能知先生(理学部)にご発表いただきます。各先生20分程度の持ち時間で、15分程度のご報告をいただき、5分程の質疑応答を予定しております。
<令和7年度第2回SDGs研究助成 成果報告会>
【日時】6月18日(水)13:20~14:50
【会場】共通講義棟1号館102室(対面開催)
【報告タイトル、報告者】
第1報告:「緑藻マリモの保全研究と附属中学校生徒の研究意欲向上に重要な実習内容 」
(嶌田智先生;理学部生物学科)
第2報告:「知的障碍者を対象としたダンスプログラム(IDダンス)の開発 」
(水村真由美先生;文教育学部芸術・表現行動学科)
第3報告:「基礎研究に基づく強相関電子系の未解明領域の探求とその革新的応用 」
(古川はづき先生;理学部物理学科)
第4報告:「安価な小型飛跡検出器の開発」
(河野能知先生;理学部物理学科)
【参加申込】
ご参加の方は、下のURLのFormsからお申込みください。
https://forms.office.com/r/suYB6cBaLQ

※人数把握のためご協力をお願いしております。
※申込状況にかかわらず、周囲の方をお誘い合わせの上、お気軽にご来場ください。
【発表概要】
第1報告
題目:緑藻マリモの保全研究と附属中学校生徒の研究意欲向上に重要な実習内容
研究者名:嶌田 智(基幹研究院 自然科学系 教授)
若菜 勇(釧路市役所 都市経営課 世界自然遺産推進室 室長)
相川 京子(前 附属中学校 校長)
植竹 紀子(サイエンス&エデュケーション研究所 特任講師)
概要: 緑藻マリモは,環境省レッドリストでは絶滅危惧 I 類に,文化庁からは国の特別天然記念物に指定されています。一方で,マリモはお土産などで馴染みがある藻類です。そこで本研究では,絶滅に瀕しているが知名度の高いマリモを用いることで,SDGs目標15[陸の豊かさを守ろう]と目標4[質の高い教育をみんなに]の達成に貢献できると考えました。保全研究では,小型マリモから大型マリモに成長する際に位置する水深別・層別のマリモの光合成特性を解析し,光環境への適応を調査しました。また,附属中学校生徒へのマリモを用いた実習では,事前・事後アンケートと半構造化面接により,科学研究への意欲やSDGsの自分ごと感が向上したか調査しました。本成果報告会では,マリモの光合成活性に関する解析結果と,中学生にとって効果的な実習内容に関して報告させていただきます。
第2報告
題目:知的障碍者を対象としたダンスプログラム(IDダンス)の開発
研究者名:水村真由美(基幹研究院 人文科学系 教授)
高橋 将(大東文化大学健康スポーツ科学部 講師)
濱名 智男(日本文化大學法学部 教授)
杉山 りん(お茶の水女子大学大学院博士後期課程院生)
概要:本研究は、SDGs「すべての人に健康と福祉を」を直接的に実現し、運動を通じた「質の高い教育をみんなに」「人や国の不平等をなくそう」といった視点から、知的障碍者が実施可能かつ運動効果が期待されるダンスプログラムを開発することを目的とした。なお知的障碍者の運動機能に関しては、先行研究がほとんどなく、運動実施に関わる課題に不明な点が多いことから、ダウン症者を含む知的障害者の運動機能を調査することにより、運動機能の中でも特に改善が求められる要素を抽出した。本研究では、知的障碍者が行う柔道(ID柔道)のウォーミングアップとして導入可能なダンスプログラム(IDダンス)を想定し、プログラム開発と現場での活用を試みた。なお身体活動量の増加は、化石燃料を用いた交通機関での移動減少に繋がることから近年WHOを中心とした健康福祉分野において「気候変動に具体的な対策」になるとも言われている。
第3報告
題目:基礎研究に基づく強相関電子系の未解明領域の探求とその革新的応用
研究者名:古川はづき(基幹研究院 自然科学系 教授)
Edward Forgan(英国バーミンガム大学 名誉教授)
Elizabeth Blackburn(スウェーデン ルンド大学 准教授)
Vasyl Ryukhtin(チェコ チェコ科学アカデミー研究所 研究員)
Robert Cubbit(フランス ラウエランジュバン研究所 研究員)
Sebastian Mühlbauer(ドイツ ミュンヘン工科大学 研究員)
Edward Foley(理化学研究所 CEMS SCSRT 技師)
Minoru Soda (お茶の水女子大学)
概要: 強相関電子系の研究は、エネルギー変換材料や電子デバイスの基盤技術として重要です。たとえば、超伝導技術はクリーンエネルギーや量子コンピュータの実現に、スキルミオンの研究は省エネルギー型磁気デバイスの開発に貢献すると期待されています。
我々は、令和6年度には、空間反転対称性が破れた超伝導体 LaNiC₂ を用いて、理論的に予言されていた新しい「ヘリカル磁束相」の実証に挑みました。そして、フランスのラウエ・ランジュバン研究所にある世界最高性能の中性子小角散乱装置 D33 を用いた実験により、その存在を世界で初めて実証することに成功しました。
このヘリカル磁束相は、非対称な結晶構造に起因する局所電場と磁場の相互作用によって現れるものです。実験では、磁場を強くするほど構造の歪みが大きくなることも確認されました。今後はこの相の特性解明をさらに進め、超伝導の理解を一層深めていく予定です。
第4報告
題目:安価な小型飛跡検出器の開発
研究者名:河野能知(基幹研究院 自然科学系 准教授)
概要:素粒子物理の実験で使う粒子検出器は、これまでX線撮像素子や高感度な光センサとして医療や様々な科学計測に応用されてきました。粒子検出器の中でも荷電粒子の飛跡を可視化することを目的としたもの(飛跡検出器)に半導体検出器があり、現在でもセンサの微細化、高速なデータ収集、放射線耐性の強化などの面で開発が行われています。ただし、半導体製造業者による特注品で高価ということもあり、高い性能が要求される部分に利用が限定されている状況です。本研究では高性能な検出器の開発ではなく、1 mm2程度の位置分解能をもつ飛跡検出器を安価に製作し、実験室での利用を広く実現することを目指しています。安価な部品を用いて多チャンネル読み出し基板を実装、検出器全体の設計、開発の現状について紹介します。

なお、6月11日(水)に第1回SDGs研究助成 成果報告会 、6月25日(水)に第3回SDGs研究助成 成果報告会 の開催を予定しております。
詳細は令和7年度第1回SDGs研究助成 成果報告会のご案内、令和7年度第3回SDGs研究助成 成果報告会のご案内からご確認ください。
関連ファイル / Related Files
»  R7年度SDGs研究助成成果報告会(第2回)(PDF形式 1,814キロバイト)
R7年度SDGs研究助成成果報告会(第2回)(PDF形式 1,814キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き、お茶の水女子大学のサイトを離れます)が必要です。