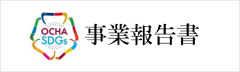- SDGs推進研究所
- 令和7年度第3回SDGs研究助成 成果報告会のご案内
ページの本文です。
令和7年度第3回SDGs研究助成 成果報告会のご案内
2025年6月27日更新
本イベントは終了しました。開催報告の記事をご覧ください。(こちら)
※本案内は、学内関係者向けです。
令和7年度第3回SDGs研究助成 成果報告会のご案内
SDGs推進研究所は、個人研究、学内外の研究者との共同研究、企業や他機関との共同研究などを対象とし、本学のSDGs研究を牽引する研究を発掘し、SDGsに資する研究活動および教育活動を活性化させることを目的とした助成を行っています。
この度、令和6年度に実施した研究助成の成果報告会を3回にわけて開催する運びとなりました。学生、教職員皆様のご参加をお待ちしております。お近くの学内者へ、ぜひご周知ください。
第3回は、刑部育子先生(生活科学部)、大瀧雅寛先生 (共創工学部)にご発表いただきます。各先生20分程度の持ち時間で、15分程度のご報告をいただき、5分程の質疑応答を予定しております。
<令和7年度第3回SDGs研究助成 成果報告会>
【日時】6月25日(水)13:20~14:10
【会場】本館113室 (対面開催)
【報告タイトル、報告者】
第1報告:「「食」の体験を通した持続可能性のための幼児教育実践研究:「食」の未来を考える素材としての「雑穀米」に着目して 」
(刑部育子先生 ;生活科学部人間生活学科 )
第2報告:「途上国におけるトイレ排水処理による病原リスク除去能力の実態 」
(大瀧雅寛先生;共創工学部 人間環境工学科 )
【参加申込】ご参加の方は、下のURLのFormsからお申込みください。
https://forms.office.com/r/suYB6cBaLQ

※人数把握のためご協力をお願いしております。
※申込状況にかかわらず、周囲の方をお誘い合わせの上、お気軽にご来場ください。
【発表概要】
第1報告
題目:「食」の体験を通した持続可能性のため幼児教育実践研究:「食」の未来を考える素材としての「雑穀米」に着目して
研究者名:刑部 育子(基幹研究院 人間科学系 教授)
宮里 暁美(お茶大アカデミック・プロダクション・寄附講座教授(元お茶大こども園園長、現お茶大こども園特別アドバイザー))
内海 緒香(人間発達教育科学研究所 特任准教授)
光橋 翠(お茶大 基幹研究院 研究員)
概要:雑穀は高い栄養価や機能性などの利点、広い環境適応能力を有することから、持続可能な作物として、世界の食料安全保障と飢餓の解消に大きな役割を果たすことが期待されおり、国連が2023年を「国連雑穀年」として設けるなど、SDGsを推進する作物として注目されています。本研究では、持続可能な社会づくりに貢献する乳幼児教育における素材として、雑穀米にどのような可能性があるかについて、お茶大こども園の食の教育実践を通して検討しました。実践を通して園児・保育関係者・保護者が雑穀米について興味関心をもち、考える過程で、雑穀がSDGsの目標2「飢餓をゼロに」、目標3「すべての人に健康と福祉を」、目標13「気候変動に具体的な対策を」の達成に貢献する作物であること、日本の食・文化・自然の多様性を支えてきた雑穀を多面的に体験することで自然の多様性に気づくことにより、本取組が目標15「陸の豊かさも守ろう」の達成にも貢献する地球的課題への学びにもつながることが示唆されました。本研究は、目標4「質の高い教育をみんなに」のターゲット4.7「全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする」に資する実践となりました。これらの実践研究の成果は『雑穀米:文京区立お茶の水女子大学こどもうれしい*おいしいプロジェクト』にまとめられました。
第2報告
題目:途上国におけるトイレ排水処理による病原リスク除去能力の実態
研究者名:大瀧雅寛(基幹研究院 自然科学系 教授)
Tushara Chaminda G.G.(スリランカ国立Ruhuna大学工学部 教授)
概要:途上国の多くの地域では水道整備に付随して水洗トイレの普及が進んでいるが、下水道の整備は進まずトイレ排水は家庭毎に設置される個別排水処理で対応している。しかし非水洗型(Pit latrine)の処理にて水洗トイレ排水を処理しているため、十分な処理時間を経ずに周辺土壌へと放出浸透している状況となっており、SDGs項目6「安全な水とトイレを世界中に」の目標達成の阻害となっていると考えられる。本研究はスリランカ国を対象とし、個別トイレ排水処理周辺土壌中の糞便由来微生物指標を調べることで病原リスクの拡散状況を把握し、適切な処理システムを提案することを目的としている。スリランカ国南部Galle地域の4か所の個別トイレ排水処理の周辺土壌を用いた調査研究の結果、下水道未整備地域においてはSDGs項目6「安全な水とトイレを世界中に」の達成には水洗トイレ対応のSeptic tankの導入が重要であることを微生物指標の測定結果から確認することができた。ただしウイルスに関してはデータ不足であり、そのためには土壌からのウイルス指標検出率の向上が不可避であった。今回、土壌中の水分量および結合水の関与を調査したが、これらの関与は小さいことが示された。

なお、6月11日(水)に第1回SDGs研究助成 成果報告会 、6月18日(水)に第2回SDGs研究助成 成果報告会 の開催を予定しております。
詳細は令和7年度第1回SDGs研究助成 成果報告会のご案内、令和7年度第2回SDGs研究助成 成果報告会のご案内からご確認ください。
関連ファイル / Related Files
»  R7年度SDGs研究助成成果報告会(第3回)(PDF形式 1,738キロバイト)
R7年度SDGs研究助成成果報告会(第3回)(PDF形式 1,738キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウインドウが開き、お茶の水女子大学のサイトを離れます)が必要です。