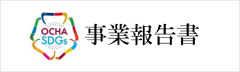- SDGs推進研究所
- 第4回文京区内大学サステナビリティ関連取組紹介のための交流・意見交換会 参加報告
ページの本文です。
第4回文京区内大学サステナビリティ関連取組紹介のための交流・意見交換会 参加報告
2025年11月10日更新
文京区内大学サステナビリティ関連取組紹介のための交流・意見交換会に参加しました
2025年10月31日に文京区民センター(東京都文京区)にて、開催された「第4回 文京区内大学サステナビリティ関連取組紹介のための交流・意見交換会」に参加しました。
「文京区内大学サステナビリティ関連取組紹介のための交流・意見交換会」は、区内の大学と区内に関連する企業が参加し、各大学・団体が日頃のサステナビリティに関する取り組みについて発表、参加者で意見交換をする会で、今回は跡見学園女子大学、中央大学、東京大学、東洋大学、日本女子大学、東京大学消費生活協同組合およびお茶の水女子大学が発表を行いました。
本研究所からはOCHA-SDGs学生委員会委員長が発表を行い、本研究所と連携して活動を行う学生組織OCHA-SDGs学生委員会の紹介と、附属学校園と連携したフードドライブの活動を報告しました。
OCHA-SDGs 学生委員会では、手話を学ぶ会である「手話べり」、自分には要らなくなったもののまだ使える物を譲る「おゆずりフェス」、「ウォーターサーバーの設置」、「附属学校園、他大学、自治体、企業との連携」といった活動をプロジェクトベースでメンバーを構成し日々取り組んでいることや「ロジックモデル(=課題とその現状に対し、手段から目的までのロジックを端的に図式化したもの)」 なども活用し未来を見据えた持続可能な活動をしていることを報告しました。
OCHA-SDGs 学生委員会では活動の大局を捉え、一枚のロジックモデルに落とし込むことを重視しています。ロジックモデルを作成することにより、(1)プロジェクトを別視点から見直すきっかけづくり、(2)プロジェクト内容の発信力向上、(3)メンバー間の交流促進、(4)モチベーションの向上、という効果が見込まれ、これがひいては「持続可能性」について議論されるときに見落とされがちな、「活動そのものの持続性」につながるという視点を提示しました。
また、本学ならではのフードドライブの特色として、幼稚園・小学校・中学校・高校・大学が同一敷地内にあるという利点を生かして全学で活動を行っていることに触れ、OCHA-SDGs学生委員会が食品ロスの削減と社会福祉の向上に寄与していることを発表しました。
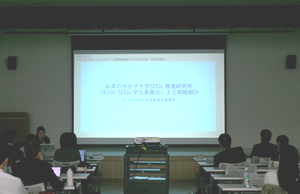
(発表を行うOCHA-SDGs学生委員会委員長)

(委員会の活動と附属学校園と連携したフードドライブ活動について発表)
本研究所の取り組みを多くの方々に関心を持っていただく機会となったのと同時に、区内の大学・企業と意見や感想を共有し相互に交流する機会となりました。
- 2024年度に行われた第3回についてはこちらの記事をご覧ください
- 2023年度に行われた第2回についてはこちらの記事をご覧ください。
- 2022年度に行われた第1回についてはこちらの記事をご覧ください。
関連リンク / Related Links
»【文京区HP】文京区内大学サステナビリティ関連取組紹介のための交流・意見交換会を開催しました (新しいウインドウが開き、本サイトを離れます)