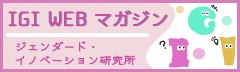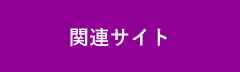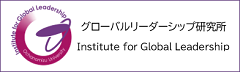- ジェンダード・イノベーション研究所
- 産官学連携・プロジェクト
- 2024年度 第3回 ジェンダード・イノベーション産学交流会報告
ページの本文です。
2024年度 第3回 ジェンダード・イノベーション産学交流会報告
2025年3月17日更新
2024年度 第3回 ジェンダード・イノベーション産学交流会報告
【日時】 2025年3月14日(金曜日)16時~18時
【会場】 お茶の水女子大学国際交流留学生プラザ2階多目的ホール
【テーマ】 交差性デザインカード
【参加者】 17機関より40名、学内関係者13名(計53名)
プログラム
司会:斎藤悦子(IGI副研究所長)
①16:00 – 16:05 開会挨拶 斎藤悦子(IGI副研究所長)
②16:05 – 16:20 交差性デザインカード説明 相川頌子(IGI特任講師)
③16:20 – 16:55 セッション1 自己紹介と「定義」の話し合い
④16:55 – 17:25 セッション2 「事例研究」の話し合い
⑤17:25 – 17:50 ディスカッション内容の全体共有
⑥17:50 – 18:00 講評 石井クンツ昌子(IGI研究所長)、加藤美砂子(IGI副研究所長)
開催報告
3月14日、2024年度の第3回ジェンダード・イノベーション産学交流会が開催されました。17機関から40名の方が出席され、本学からの出席者13名を合わせた53名が会場に集まりました。今回のプログラムは、ジェンダード・イノベーション研究所で翻訳した、日本語版『交差性デザインカード』を用いたワークショップです。
交差性デザインカードは、デザインや開発のプロセスの中で交差性に関する諸課題に気付くためのツールとして、ロンダ・シービンガー教授率いるチームが開発し、2021年にStanford University Pressから出版されました。IGIでは、2023年の11月にシービンガー教授をお招きし、「Intersectional Design Cardsを用いたワークショップ」を開催しました。今年度はこのカードの翻訳に取り組み、2025年4月上旬に、日本語版のカードがお茶の水学術事業会から出版される予定です。今回の産学交流会は、その出版に先立って、日本語版交差性デザインカードに触れていただく機会となりました。
交流会では、相川頌子特任講師によるジェンダード・イノベーションと交差性デザインカードの説明の後、6つのグループに分かれてワークショップを進めました。交差性デザインカードは、交差性要素のカード12枚、デザイン検討のための問いのカード12枚、事例研究のカード16枚で構成されています。今回のワークショップでは、交差性要素と事例研究のカードを使う2つのセッションを行い、セッション毎に、各グループで話し合った内容を全体共有していただきました。
セッション1では、グループで着目する交差性要素として「地理的な場所」をあげるグループが多くありました。また、交差性要素カードに含まれていない交差性要素として、役職、職種、体質、ITリテラシー、外向的か内向的かといった性格等が提案されました。
セッション2では、セッション1で選んだ交差性要素に関連する事例をひとつ選び、話し合っていただきました。以下は、A~Fの各グループでのディスカッション内容の要約です。
A 「機械学習におけるデータバイアス」を取り上げた。生成AIそのものにはジェンダーはないはずだが、ユーザーは生成AIを男性か女性のどちらかだと思って使っている可能性がある。ロジカルなので男性、親しみやすいので女性といったイメージもある一方で、性別については意識せずに使っているという人もいた。
B 「遊び場」をめぐる議論が盛り上がった。ジェンダーの観点では、男の子と女の子では遊具の使い方が違う。年齢の観点では、大人がひとりで公園にいると変な目で見られるといった問題もある。公園を、全世代が楽しめる某テーマパークのような場所にするにはどうすればよいかということを話し合った。
C 「遊び場」について議論をした。様々な障害への配慮が行き届いた遊び場を作るのは難しいと思われる。公園は子どもたちにとって安全な場所であって欲しいが、公園を開かれた場所にすると安全を保つことが難しくなるといったジレンマもある。
D 「遊び場」について議論した。ほかのグループから「男女で遊具の使い方が違う」という話が出たが、私たちのグループでは、女の子だけの場所を作るのは良いことだと話した。また、高齢者の利用のしやすい公園とはどのような公園か、安全な場所にするには有料にした方がいいのではといったことも話した。また、公園の中のトイレについて、ジェンダーレストイレがあると、子育て中の男性は助かるだろうという話も出た。
E 事例をひとつ選ぶということはできなかったが、家族構成がどのようにサービスに影響しているかを話し合った。月経カップは、シングルファーザーの娘はアクセスしにくいだろう。シェアライドについては、高齢となった時に近距離で使えると良いと思うが、過疎地域では使いづらい。これらの例には交差性が特に関係していそうだという議論をした。
F 「仮想アシスタント」について議論した。仮想アシスタントは、音声のデフォルト設定が女性。一度男性の声が聞こえて驚いた時に、自分の中のアンコンシャスバイアスに気づいた。会社のチャットボットのアイコンが女性の会社も多いが、最近ネコに変えた。ネコに変えたことで不快に思う人が減ったのではと思う。配膳用ロボットがネコ型なのもそうした配慮かもしれないといった話があった。
セッション終了後、石井クンツ昌子所長と加藤美砂子副所長からの講評がありました。石井先生からは、「各グループのディスカッション内容から、多様性の中のダイバーシティというようなことを感じ取ることができた。ITやロボットに関心を持っているが、これらもジェンダーが関わっている。交差性デザインカードについては、今回のワークショップの経験をもとに、内容を工夫しながら、現場で使っていただきたい」とのコメントがありました。加藤先生からは、「短時間でさまざまな意見が出されることにワクワクしながら聴いていた。身近な話として、現在はスマホを持っていない人がIT弱者となっていると感じている。また、左利きの方が多くみられるようになり専用の道具も増えているようだが、左利き用の歯科医手術台が少なくて教育現場では取り合いになっているという話もある。ぜひ産業界で取り組んでいただきたい」とのコメントがありました。
限られた時間ではありましたが、どのグループでも、終始、和やかでありながらも活発な議論がなされていました。今後、各所で日本語版交差性デザインカードが用いられ、国内で交差性に着目することの重要性についての認識が広まっていくよう、ジェンダード・イノベーション研究所でも努めていく所存です。

(相川特任講師による説明)