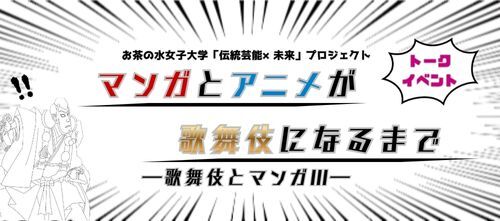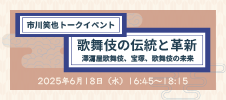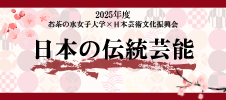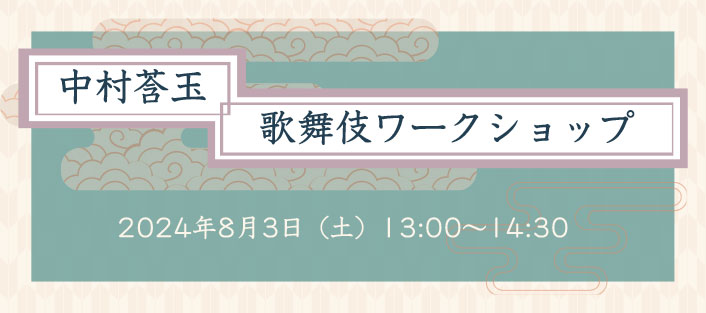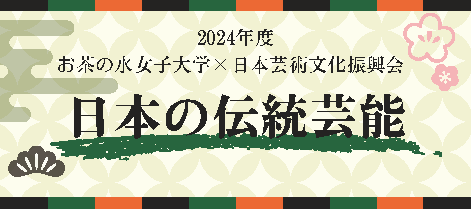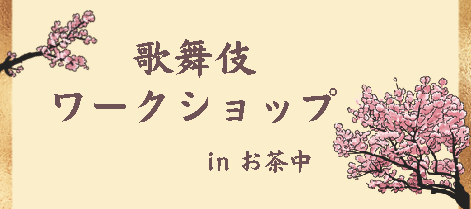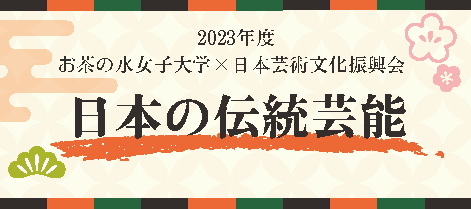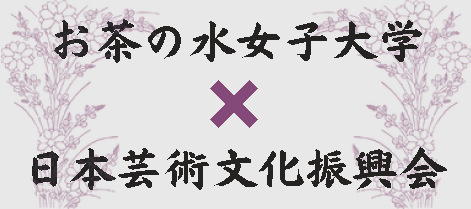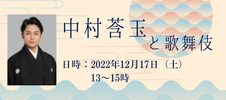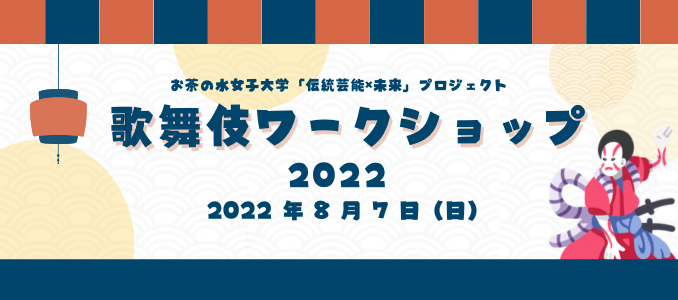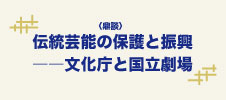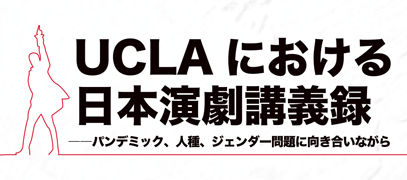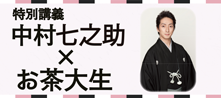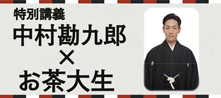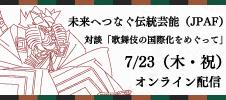- 「伝統芸能×未来」プロジェクト(JPAF)
- イベントレポート
- イベントレポート トークイベント「大河と歌舞伎と娯楽映画――ドラマの面白さの根本とは?」
ページの本文です。
イベントレポート トークイベント「大河と歌舞伎と娯楽映画――ドラマの面白さの根本とは?」
2024年11月28日更新

会場の様子

吉川邦夫さん

大森洋平さん
2024年1月15日お茶の水女子大学において、吉川邦夫さん(演出家、ドラマ制作者)と大森洋平さん(NHKドラマ番組部、シニア・ディレクター)を講師にお迎えして「トークイベント 大河と歌舞伎と娯楽映画」を開催しました。
吉川さんはNHKで大河ドラマ『新選組!』『真田丸』をはじめとする数々の名作ドラマにディレクターとプロデューサーとして関わり、現在はフリーランスとして活動しています。大森さんはNHKでドラマやドキュメンタリーの時代考証を担当し、そのお仕事の様子は著書『考証要集 秘伝! NHK時代考証資料』(文春文庫)などによって紹介されています。
参加者は本学学部生、大学院生、教職員、附属校生徒の計80名です。「心に残る大河ドラマ」という事前アンケートでは一位が『真田丸』で二位が『鎌倉殿の13人』でしたが、『おんな太閤記』や『黄金の日々』といった作品名もあげられ、年季の入った大河ドラマファンがいることもうかがえました。映像制作の第一線で長年ご活躍のお二方のお話は実に刺激的で、質疑応答も含め120分ノンストップの熱気溢れるイベントとなりました。
冒頭、大河ドラマの制作手法について『真田丸』などの具体例をもとにお話いただきました。制作にあたっては番組開始以来の伝統やノウハウをベースにしながら、常に「なぜ今この時代や人物を扱うのか?」ということを自問自答し続けてきたといいます。過去の出来事を通じて今を見つめる姿勢ゆえに、大河ドラマは戦後日本を代表する映像コンテンツであり続けてきたのでしょう。ストーリーテリングと人物造形については、「今の価値基準で作らない」(吉川さん)、「自由な発想を〈歴史のフレーム〉の中に留まらせることが大切」(大森さん)という言葉が印象的でした。
学生のうちに見ておくべき演劇と映像作品という話題では、リストをもとに「大河ドラマ」「時代劇」「クロサワ時代劇」「歌舞伎」「西部劇」「ジョン・スタージェス監督の活劇」「サスペンス洋画」「ヒッチコック映画」「歴史映画」「音楽映画」というテーマ別にそれぞれのおすすめ作品を複数ご紹介いただきました。お二方の古今東西のエンターテインメントに対する豊富な知識に圧倒され、優れたエンタメ作品から学ぶべきことは数多くあるのだと痛感しました。最後にエンターテインメントの存在意義をお話しいただきましたが、優れたエンタメは、今を生きる人々の価値観を揺さぶる強い力を持つとともに、優しく寄り添ってくれる存在でもあるのだと感じました。
質疑応答では参加者からの多くの質問に丁寧にお答えいただき、終了後も個別にお話をうかがいたいと講師の回りに長蛇の列ができるほどの熱気でした。参加者のこれまでの大河ドラマの鑑賞歴や思い入れは様々でしたが、お二方の作品作りに対する熱意と愛情、そして真摯な姿勢に感銘を受け、多くの刺激と学びを得たようです。終了後に実施したアンケートにはそうした思いがこもったコメントが多く寄せられました。以下に、代表者によるイベントレポートと、参加者アンケートの抜粋を掲載します。
代表者によるイベントレポート
幼少期から大河ドラマを夢中で視聴し、ドラマを通して歴史の面白さに触れ、多くの学びを得てきた私は、まさか本学でこのようなイベントが開催されるとは夢にも思っておらず、当日を何ヶ月も前から楽しみにしてきました。当日もドラマ本編を再視聴し、劇伴を聴き込みながら会場に向かいました。
本イベントでは、ゲストのお二方が携わられた大河ドラマ『真田丸』の制作裏話を中心に、ノンストップで2時間たっぷりとお話しいただきました。キャスティングの方法・音楽・衣装のお話からお二人のキャリアについてまでお話は多岐にわたりましたが、本当にあっという間の2時間で、またどれもあまりに貴重なお話でしたので、ファンとしては一言一句取りこぼさずにメモして帰りたい気持ちでした。
これまで、私自身が歴史ドラマを好んで視聴してきた一方で、周囲には“歴史ドラマはほとんど見ないし興味もない”という人が多く、同世代となかなか会話ができないもどかしさを感じてきました。しかし、本イベントの参加者の皆さんには、“歴史ドラマが好きで、これまでも熱心に視聴してきた”という人たちが多かったばかりか、イベント終了後もゲストのお二人に質問をしたい人たちが長蛇の列を作る光景も目の当たりにして、実は身近にも、ドラマを通して歴史を面白い、楽しいと語り合うことのできる同世代が存在していたことがわかり、とても嬉しかったです。
大河ドラマは、「知識がなくてわからないから見ない、楽しめない」コンテンツではなく、イベント中のお話にもあったとおり「見たら面白かった」、「見たら分かるようになった」、「面白かったからもっと深く知りたい」が自然に叶うコンテンツだと、私は思っています。これは歌舞伎についても同じことが言えるのではないかと思いますが、本イベントを通して、一ファンとしては、“入りにくそう、難しそう、歴史は苦手”と感じている同世代にこそ、大河ドラマをぜひ視聴してほしいと改めて強く感じました。ゲストのお二人がお話しされていたように、衣装・言葉・思想・風俗…と、細かなところまで時代考証がなされ、プロデューサーや脚本家・役者の方々によって作り込まれているという大河ドラマは、単に楽しく“娯楽”のつもりで視聴していても、知らず知らずのうちに知識が増え、かつては多くの人が共有していた「歴史のフレーム」が自分の中に構築されていきます。これは他の伝統芸能を見る上での前提知識となり、他の芸能をより深く理解し、楽しむための手助けにもなるはずです。
また、今回のイベントでは、お二人から参加者に向けて「おすすめの大河・歌舞伎・映画リスト」のお土産も頂きました。世の中にコンテンツが溢れ、サブスク等で簡単に視聴することができる今、かえって私は“何から視聴していいのかわからず視聴ができない”という事態に陥りがちでしたが、頂いたリストを参考に少しずつ試聴するのを今後の楽しみにしたいと思っています。
最後になりましたが、吉川さん、大森さん、貴重なお話を本当にありがとうございました。 今回時間の関係で、大森さんに、朝ドラ『カムカムエヴリバディ』で評判になった、現代語の「時代劇言葉」への変換を実演いただくことは叶いませんでしたので、それも含めて、第二弾の開催を心待ちにしています。
人間文化創成科学研究科 博士前期課程2年 土屋はる野(所属は当時)
参加者アンケートより抜粋
- 『新選組!』は小学校4・5年生で視聴して「大河ドラマって大人が見るもので、難しくてよく分からない時代もの」から「我々子どもでも観ることができる、共感することができるもの」と一気に身近に感じた作品でした。当時はまだ「新選組」という名前すら知らず、「慎吾ちゃんが出てる!」から見始め、「昔は有名な人物以外にも日本を動かそうとした人がいたんだ」という興味へ変わり、自由研究として題材を掘り下げたり、テーマ曲を練習して学校行事で演奏した程に思い入れがある作品です。年齢を重ねて様々な史実を知った上で本日のお話をうかがい、歴史をエンタメにするにあたっての「軸とは何か、枠とは何か」を考えることができました。お話を踏まえて『新選組!』を見返したいと思います。
- 長年テレビドラマのファンであり様々な作品を楽しんできましたが、正直なところ大河ドラマは堅苦しい印象があり敬遠していました。しかし今回、三谷幸喜氏が脚本を手がけたお話を聞いて、その新しいアプローチや反感を買いながらも挑み続けた姿勢に興味津々で、見逃してしまったことを後悔しました。特に他のテレビドラマとは異なり、大河ドラマは元ネタとなる歴史的な出来事が存在し、その中でどのようにストーリーを構築し視聴者を引き込むかという制作の舞台裏についてのお話が非常に面白かったです。今回のイベントを通じて、大河ドラマの新しい側面やその制作に関わる様々な工夫に触れ、これからは新たな視点で楽しむことができそうです。
- 「時代考証は作品の大枠であり、その中で自由に遊んで物語を作る」という言葉が大変印象に残りました。近年時代考証がネット上で問題になることがあり、歴史物に車が映りこんだりすると炎上したりしますが、制作側は「煩わしい」と感じているのではないかと思っていました。しかし制作側は言葉選び一つにも悩みながら制作していて、時代考証に対してとても誠実だと感じました。歌舞伎も歴史上の事件をテーマにしたり既にある作品から枠組みを取り入れたりしますが、歌舞伎のほうが時代考証の枠組みがゆるく、大河ドラマのほうががちっとした枠組みのもと作られていると感じました。どちらが良いというわけではなく、歌舞伎は歌舞伎、大河ドラマは大河ドラマの良さがあると思いました。
- 大河ドラマが一年を通じて一つの作品を完成させるということは知っていたのですが、それを作成するにあたり様々な苦労があることを、実際に制作に深く関わるお二方からうかがえたことに大変感動しました。特に感銘を受けたのは音楽のお話でした。大河ドラマはNHK交響楽団によるフルオーケストラの豪華な音楽が魅力ですが、『真田丸』の曲をつくるにあたって真田VS徳川の泥臭い戦いを醸し出すために木の匂いを感じさせるようなヴァイオリンの独奏を入れたというエピソードに非常に驚きました。曲を作るにあたってそのような細やかな表現の工夫がなされていたことを知り、大河ドラマの奥深さを感じました。楽器の特性の面から考えるとヴァイオリンなどの弦楽器は他の楽器に比べて切り込みを入れるような音の鋭さがあり、刀が振りかざされる戦乱の世がテーマである『真田丸』にぴったりだと思います。今後大河ドラマを視聴する際は音楽にも着目して楽しもうと思います。
- 心に残る作品には、心に残る理由があることを知りました。「時代のフレーム」「創造することにも根拠を作る」「行間」など、今までなんとなくいいと思っていた作品がなぜいいのか納得することができました。大河ドラマは普通のドラマより心を大きく揺さぶられる気がしますが、それは日本人の感情を一番現しているからだと知り、まだ見ていない作品も見たくなりました。卒業後の進路は今回のテーマとは関係ない業界ですが、過去から学ぶことや自分の興味あることを見直すことなど、心に残しておきたいと思うお言葉がたくさんありました。
- 今回のお話を聞いて、歌舞伎をもっと観に行こうという気持ちになりました。大河ドラマは15年近く見てきましたが、これまで他のドラマや映画、舞台を観に行く機会を持っていませんでした。大学に入って狂言を始めたことをきっかけに、お能や歌舞伎、文楽を数回観に行ったのですが、初めて観たわりには馴染みがあると感じたのは、それらが土台となった大河ドラマをずっと観てきたからかもしれないと思います。歌舞伎役者さんが大河ドラマに出演される理由の一つも、古典を極めることで培ったお芝居にあるのかなと思いました。大河ドラマが好きな私にとっての宝庫が古典芸能のように感じます。積極的に観に行きたいです。
- 2時間では足りないくらいの充実した内容でした。歴史とエンターテイメントの間を埋めるものは何か、非常に興味深く聞かせていただきました。NHKのノウハウの蓄積、個人の仕事か組織の仕事かのお話、ゲストお二人の知識と経験の豊富さが印象深いです。視聴者がSNSを通じて史実の披露や感想の交換が行われる中で制作の難しさは過去作よりあると思いますが、『真田丸』の時のように力になっていくこともあると思います。私は観劇も趣味で作劇というものが好きなので、ドラマにはある程度自由でいてほしいと思っています。ドラマがきっかけで史実に近づいていくこともあるのでは。そうあって欲しい。歌舞伎の世界は史実やポリコレの矢に刺されることはまず無いのに、ドラマに対しては受け取る側の姿勢が違うのでしょうか。劇場の椅子に座るように、まずはその作品の世界観に浸る姿勢で大河ドラマを見続けたいと思います。
- 今回のイベントに参加し、元々『真田丸』が大好きだったのでそのお話をたくさんうかがえてとても楽しく、学ぶことも多かったです。大河ドラマはもちろん時代劇について、「命のやり取りや戦争などは、現代劇では視聴者から距離が近いため難しいこともあるが、時代劇としてしまえば描くことができる」というお話がありましたが、歌舞伎やその他の舞台芸術においても言えることではないかと感じました。歌舞伎や大河ドラマなら人がたくさん亡くなってしまっても見ることができて、それによって伝えたいことをしっかりと表現できるということは、こうした芸能が存在する意味の一つとも言えるように感じました。
- 「現代の視点で過去を語ってはいけない」というお言葉が印象に残りました。それが今回の話題の一つであった時代考証とも繋がりますし、時代劇・歴史劇は「未来へのバトン」であり、時代ごとの文化や技術、服飾、所作等の大切なものを伝える役目を果たしていることを学びました。他にもたくさんの興味深いお話があり、あまり大河ドラマに明るくない私ですが、制作の背景や物語の時代背景などを考えて楽しみながら、まずは『真田丸』から見てみたいと強く感じました。
- 小学生の時に『龍馬伝』から大河ドラマを見始め、高校生のころ勉強の合間に見ていた『真田丸』が一番好きな私にとって、今回の講演はとても興味深いものでした。中でも印象に残ったのは、「時代考証とは何か」についてです。仕事内容の実情を知らず、「いかに正確に再現するかに苦心する役割」というイメージを持っていましたが、お話をうかがい、描きたい現象やシーンに整合性や根拠を与えることや、逆に何を鑑賞者の目に触れさせないかということがむしろ大切な役割なのだと学びました。また、物語の枠組みを設定することについても、現代の価値観を登場人物に代弁させないことや、フィクション特有の「あそび」の保守につながるということがとてもよく理解できました。『真田丸』の評判とSNSの関係についても印象に残りました。見始めた当初は長澤まさみさん演じるきりに「違和感」を感じていたものの、次第になくてはならない存在となりましたし、その印象の変化のきっかけの一つがTwitterだったと記憶しているからです。否定も肯定も飛び交うSNSの影響で、次第に作品への評判が醸成されていく感覚は実感を伴って理解できます。最後に、NHKという看板を背負い、一年という長い期間ドラマを放映し続けることの難しさを知るとともに、そこに関わるプロフェッショナルの皆様の熱意と覚悟と自負などを感じることができました。
- とても充実した時間でした。お話がとてもおもしろく興味深かったのはもちろんですが、一番ありがたかったことは、講師お二方の仕事への姿勢をうかがえたことで、大変なこだわりによって作品が生まれ、世の中に出ているということを実感しました。ご自身で勉強を重ねて、先人からのたくさんのバトンを見つけ、それを解釈して引き継いでいることに感動しました。伝統や歴史は新しいものを創出する土壌として、文化が豊かになるために必ず必要なものだと思います。『新選組!』の大河ドラマとしての新しさを感じましたが、それまでの大河ドラマにも真剣に向き合ってきた方々だからこそ、新しくすることができたのでしょう。関わる分野は違えども、私も先人たちの蓄積に気付き、バトンを受け継ぎ、新たな歴史を築く人でありたいと思いました。